
Peak Design (ピークデザイン) アウトドア バックパック レビュー:登山 × カメラ × デイリーユースとこれ1つで文字通り何でもこなせる。魔法のような仕掛けが詰まったクロスオーバー・バックパック
Peak Design(ピークデザイン)といえば、カメラを趣味とする人なら一度は耳にしたことがあるかもしれません。
カメラマウントやバッグをはじめとしたカメラ関連アクセサリの開発から始まり、最近ではトラベルバッグやスマホ用アクセサリーなど、日進月歩で活躍のフィールドを広げる新進気鋭のメーカー。2010年に初めてKickstarterで発表したカメラキャリーデバイス「Capture」での衝撃的なデビューで瞬く間に世界中のカメラ愛好家を虜にし、以来これまでに11回のKickstarterキャンペーンで通算3,600万ドル(約51億5千万円)を調達※。世界で最も成功したクラウドファンディング企業といっても過言ではありません。
※出典:Huckberry “This Isn’t About Dying. This Is About Living.”
僕がピークデザインと出会ったのも、このCaptureがきっかけ。今から10年以上前のWEBサイトを始めたばかりの頃、レビュー用の撮影で山にカメラを持ち運ぶことが多くなり、ちょうどいいカメラの携行方法を模索していたところでした。そんな時、このサンフランシスコの無名ブランドが発明したこのデバイスに出会い、そのユニークなアイデアと徹底した作りの良さに胸を打たれたというわけです。それからというもの、自分はこのCaptureの歴代モデルはもちろん、カメラストラップやカバー、トライポッドといった山でのカメラ関連アイテムをすべてピークデザインに揃えて今でも愛用し続けていました。
今回のレビューは、そんなピークデザインがついに開発したアウトドア向けバックパック「Outdoor Backpack(アウトドア バックパック)」です。幸運なことにこの夏じっくりと使ってみることができました。さっそくレビューをお届けします。
なお今回は容量別に3種類あるアウトドア バックパックのうち、最もフルスペックの機能を搭載した45リットルモデルを中心にレビューしています。サイズの違いを除けばどれもおおむね同じ評価といって差し支えないので(特に違いがある場合は本文中で指摘しています)、他サイズについてもこちらを参考にしてみてください。
目次
- Peak Design「アウトドア バックパック 18 / 25 / 45L」バックパックの主な特徴
- 主なスペックと評価
- フィールドで実際に使用した詳細レビュー
- 収納力と使い勝手:神の宿った緻密な細部の工夫と無限の可能性を秘めた独自のエコシステムが、文字通り都市とフィールドをシームレスに繋ぐ
- メイン収納アクセス1:ロールトップ式とUltra Cinch™(ウルトラシンチ)システムによるスマートなデュアルアクセス開口部
- メイン収納アクセス2:クラムシェル方式による背面からの簡単な出し入れ
- 外部収納1:フレックスポケットと実用的なポケット類
- 外部収納2:用途に合わせて自由にアタッチメントをカスタマイズできる「Cord Hook™」システム
- 他製品との連動性(エコシステム):「Cord Hook™」システムとモジュール設計による無限の拡張性
- 背負い心地と耐久性:いずれも登山用バックパックとして高いレベル
- まとめ:山もカメラも本気の人は迷わずチェック。決して誰も真似できない登山×カメラ×デイリーの垣根を超えたクロスオーバーな魅力
Peak Design「アウトドア バックパック 18 / 25 / 45L」バックパックの主な特徴
Peak Design「アウトドア バックパック」は、カメラ好きの日々の暮らしから旅行、そして本格的なアウトドアまで、多様なシーンをシームレスに繋ぐ多彩な機能が詰まったアウトドア・カメラ・バックパック。米Kickstarter でもおよそ350万ドル(約5億1500万円) を獲得。旅行やハイキング好きでカメラにも妥協しない山好き・写真好きにとって最適な機能性と汎用性を備え、大切なカメラを抱えて山・旅行・デイリーと幅広いフィールドを1つのバックパックで行き来したいというユーザーに最適です。
軽量でありながら高い耐久性と耐候性を持つ素材を採用し、洗練されたミニマルなデザインにまとめ上げられたボディは、背負い心地と安定性にも優れた背面システムを備え、カメラを含めたたくさんの荷物を長時間運んでも快適さを維持します。
収納面でもピークデザイン製品に共通する独自のスマートな機構が満載。ロールトップと背面パネルの両方からアクセス可能なデュアルアクセス・スタイルはカメラ機材のスムーズな出し入れを可能にし、容量の拡張性にも優れています。付属の取り外し可能なコード類や同社のスリングバッグやカメラキューブ、パッキングキューブなどを組み合わせてユーザーが用途に応じて収納をカスタマイズできるモジュール設計など、用途や荷物の内容に合わせて最適なパッキングにカスタマイズすることができます。ラインナップは18Lと25L、45Lの3つのモデルがあり、それぞれが異なる用途に対応しています。
お気に入りポイント
- 拡張性のあるロールトップと背面から容易にアクセス可能なクラムシェル式を組み合わせたメイン収納
- 外部に張り巡らされたコードレールと付属のコードロックを合わせた自由度の高い外部収納システム
- 同社のパッキング製品と連携することで好みに合わせてカスタマイズできる収納システムと高い多用途性
- 耐久性と耐候性に優れたリップストップナイロン生地
- 背面調節可能なストラップ式ショルダーハーネス(45L)
- 丈夫な背面フレーム・パネルとタフなパッドによる安定感抜群の背面システム
- 用途に合わせて脱着が可能なヒップベルト(45Lは標準装備、25L以下は別売り)
- 未来感のある先進的なデザインで、街での日常使いにもマッチ
気になるポイント
- 素材は軽いがパーツ類が多いため重量は軽くない
- 製品の魅力を100%引き出すには、別売りの追加モジュールが必要となる
- 雨蓋がないため、雨がフロントフレックスポケット内に溜まってしまう(レインカバーは別売り)
- 収納システムやパーツ類は使い方を理解すれば便利だが、使いこなすにはやや時間がかかる
- アタッチメントのコード類の余りがぶらぶらと垂れ下がりがち
主なスペックと評価
フィールドで実際に使用した詳細レビュー
収納力と使い勝手:神の宿った緻密な細部の工夫と無限の可能性を秘めた独自のエコシステムが、文字通り都市とフィールドをシームレスに繋ぐ
本レビューではまず何よりも、いろんな意味で久々に度肝を抜かれた収納システムから触れます。正直これほど隅々まで収納の工夫が凝らされた山用バックパックは初めて。
市場の優れたアウトドア・バックパックやカメラバッグを隅々まで研究し、3年以上の歳月をかけて開発したという「アウトドア バックパック」は、パック単体での収納性の高さはもちろんですが、何よりもそれに加えて無限に広がるカスタマイズ性・拡張性の高さが最大の特徴だといっても過言ではありません。その画期的な収納システムは「メイン収納アクセス」「外部収納」「他製品との連動性(エコシステム)」という3つの視点から説明できます。
メイン収納アクセス1:ロールトップ式とUltra Cinch™(ウルトラシンチ)システムによるスマートなデュアルアクセス開口部
メインコンパートメントの2つのアクセス方法を組み合わせた「デュアルアクセス」スタイルには、のっけからガツンとやられました。
まずバックパックの基本的な構造は口をクルクルと丸めて収納するいわゆるロールトップ式で、当然大きく口が開いて荷物の出し入れはスムーズに行なえるし、また荷物の量によってパックの大きさを柔軟に調節することもできるというメリットもある。それ加えて芯材が入って丸めやすい開口部にはマグネットが仕込まれており、自然に口がピタッと正しい位置に閉じられるようになっていて畳みやすいという細かな使い勝手の良さもGOOD。
そしてさらに感心なのは、ピークデザインらしさはそこだけにとどまらず、開口部の開閉方法がまたユニーク。
開口部をクルクルと丸めてから、従来のようにバックルで固定するタイプではなく、フロントパネルに繋がったコードを片手で引っ張って締め上げることで口を閉じる「Ultra Cinch™(ウルトラシンチ)」システムを編み出しました(18リットルモデルは除く)。なるほど、両手でバックルを操作するよりも簡単で素早く、締め上げることでパック全体も適度に圧縮して弛みがなくなる。さらにこのロールトップとフロントパネルとの間に伸縮性のあるポケット(フロントフレックスポケット)を配置することができ、ここに雨具や防寒着、あるいはハイドレーションブラダーなどをセットしておけば、それらの荷物に素早くアクセスすることも可能になっています。つまりこの機構1つでロールトップの開口部とフロントポケットの開口部とを兼ねることができているという訳です。

トップ開口部は「Ultra Cinch™(ウルトラシンチ)」システムによる開閉方式。ロールトップを丸めた後、フロントポケットにもなるパネル部分にあるドローコードを引き締めると、自動的にロックされる仕組み。
ちなみにコードは一度締めたら真ん中のタブを引かない限りはしっかりと固定されているので、緩んだりする心配はありませんでした。
ただ、締め上げる際の引っ張り方には多少の慣れが必要であったことも否めず、その使い勝手には賛否両論があってもおかしくはないと感じたのは確かです。それだけでなく個人的にこの構造で最も気になったのは、このUltra Cinch™システムによる蓋は密閉されているわけでも雨蓋のように上から覆っているわけでもないため、雨が降るとフロントフレックスポケット内に雨水が溜まりやすいということです。多少の雨ならば浸水することは無いのですが、雨の心配をせずに使うには別売りのレインフライもセットで購入することが望まれます。
メイン収納アクセス2:クラムシェル方式による背面からの簡単な出し入れ
メイン収納へのもう一つのアクセス方法は、背面パネルがジッパーで完全に開くクラムシェル方式によるアクセスです(上写真)。これはBCスキーのバックパックを知っている人ならば「ああ、あれね」となるやつですが、背面パッドの周りを逆U字型にジッパーが配置されており、そのジッパーを全開にすることでスーツケースのようにメイン収納全体が大きく開きます。見ての通り荷物の整理やパッキングが非常に簡単になり、底にあるものもすぐに出し入れできます。ユーザーにフォトグラファーを多く抱えるピークデザインですから、当然カメラ機材などの頻繁な出し入れを想定してるはずで、この仕様は納得です。
またこの全開した状態の開口部は、ピークデザインのカメラ保護ケース「カメラキューブ」がジャストサイズで収まり、しかもバックパックと連結して固定することができるようになっているため、これらを組み合わせれば煩雑なカメラ機材も安全に山で携行し、容易に出し入れすることができます(下写真)。
実際に登山でミラーレス一眼レフと大三元ズームレンズのうちの2つ(標準・広角)、そして360度動画カメラをまとめて持ち歩いてみた限りでは、機材の収納性と安全性に優れたカメラキューブはやはりカメラの持ち運びに最適で、スムーズな出し入れと万が一での安心感で、高価な機材を運ぶストレスや不安を感じることなく行動することができました。すでにカメラキューブを持っている人ならば、このバックパックに乗り換える価値は十分アリだと感じます。
カメラの携行について触れいているついでに、もっと素早くカメラにアクセスしたいという人のために、このバックパックには「Capture用の接続ポイント」がショルダーハーネスとヒップベルトに標準で備わっていますので、一瞬でも撮影機会を逃したくないというシビアなフォトグラファーにもしっかりと対応しています(下写真)。
外部収納1:フレックスポケットと実用的なポケット類
外部の収納システムも秀逸です。それらは「山岳地域でのさまざまなアクティビティに対応 × カメラ機材の携行」の2点をしっかりと踏まえられています。
まず両サイドには深く伸縮性のある「フレックスポケット(端的に言うとストレッチ素材で作られたポケット)」が配置され、これは三脚の収納にぴったり。他にもテントポールやトレッキングポール、アンブレラ、保温ボトルなどの縦長水筒(その気になれば2Lのペットボトルも!)にも対応します(下写真)。
45Lモデルの場合はさらに浅型でサイドからアクセスできるストレッチポケットが追加されています。テストではここにペットボトルを入れて行動し、立ったままザックを下ろさずに出し入れすることができました(下写真。ただこの浅型ポケットは深型ポケットとスペースを共有しているため、深型に大きな荷物を入れてしまうと浅型が使えなくなるということは注意が必要です)。
さらにこの「フレックスポケット」はショルダーハーネスの左右にもメッシュ素材で配置されています。ランニングベストから着想を得て設計されたであろうこれらのポケットには、スマートフォンやスナックはもちろん、ソフトフラスクなど、歩きながらでも簡単に素早くアクセスできます(下写真)。
フロントパネルの両サイドには、2つのスリムな縦型ポケットが配置されています。地図やスマートフォン、財布、鍵などの厚みの少ない小物を入れるのに適しています。片方のポケットには取り外し可能なキーテザーが付属しており、鍵をなくす心配がありません。
ただこの縦型ポケットはジッパーが縦についている構造のため、物が落ちやすく、小物をバラバラとたくさん入れるのには適していません。その意味で、コンパスやホイッスル、ライター、日焼け止めやリップ、バッテリーやSDカードなどの小物を安心して収納するための雨蓋ポケットの役割を担える収納が、標準では付いていないことはやや気になるところです。
外部収納2:用途に合わせて自由にアタッチメントをカスタマイズできる「Cord Hook™」システム
先ほどこのバックパックの真価は無限に広がる拡張性の高さであると書きましたが、それは使えば使うほどスルメのように味わい深く分かってきます。端的に言い切ってしまうと、これは単なるバックパック(=袋)ではなく、背負う人が目的やその日の荷物に合わせてその都度自由に創り上げる(=カスタマイズする)ことができる「収納システム」だったのです。
それを形作る機能のひとつが、外部アタッチメントシステム「Cord Hook™(コードフック)システム」でした。
「Cord Hook™システム」の基本的な機能を簡単に説明すると、バックパックの周囲にちりばめられた多数の「Cord Rails(コードレール)」と呼ばれるアタッチメントポイント(取り付け用の輪)と、標準で付属している伸縮性のあるフック付きキャリーコード「Cord Hook™ストラップ」とを組み合わせることで、ユーザーが自分の好きな場所に、様々な荷物を自由に固定することができる外部アタッチメントシステム。
コードレールはフロント・バック・トップ・ボトム、あらゆる場所に設置されており、想像できるたいていの場所にフックを掛けることができます。標準付属のキャリーコードは長くて伸縮性のないコードと、短くて伸縮性のあるコードがあり、これを駆使することで、例えばボトムやトップにテントや寝袋、マットレスなどを固定したり、フロントやサイドにポールやアックスなどを固定したり、サイドポケットに入れた三脚やポールをよりしっかりと固定したりすることができます。これによって45リットルという公式の容量からはるかに大きな積載量が可能となり、これがあれば正直、長期のハイキングも不可能ではないと感じました。
他製品との連動性(エコシステム):「Cord Hook™」システムとモジュール設計による無限の拡張性
この「Cord Hook™システム」、これまでも多くのバックパックで、いわゆる「デイジーチェーン」といった機能があったじゃないか、と思われた方もいるでしょう。ただ一見同じように見えますが、深く見ていくと実際にその2つには大きな違いがあります。
従来のデイジーチェーンとCord Hook™システムとの大きな違いは、その統一性と他製品との連動性、つまりエコシステムの有無にあるといえます。一般的なバックパックにとってデイジーチェーンはバックパックのある部分に付いているパーツにすぎず、また部位ごとに大きさや形などの仕様が異なっていたりします。これに対してCord Hook™システムでは、バックパックのあらゆる部位に同じ作りのループが張り巡らされており(もちろん闇雲にではなく、計算された位置に)、それだけでなくこのループはアウトドア バックパックだけに限らず、スリングバッグやスタッフサックなど、ピークデザインの他の製品にも搭載されているのです。
例えばこのアウトドア スリングバック(下写真)。2 / 4 / 7リットルと3 サイズのバリエーションがあります。
単体としても携行のしやすさ、優れた収納を備えた便利なスリングバッグですが、ここにもコードレールが要所に搭載されていることが分かるかと思います。このコードレールと、バックパックの上部にあるコードレールをコードフックで接続すれば、あっという間に足りないと思っていた雨蓋がバックパックに搭載できたではないですか!(下写真)
普通にしっかりと固定できます。外から見ても、標準で付いている雨蓋とまったく違和感がありません(下写真)。
他にも、2Lの小さめスリングはストラップを外し、普段は胸ストラップだった部分に接続すれば、ちょうどいいフロントポケットに(下写真)。
あるいは追加でヘルメットホルダーを購入すれば、岩稜帯ルートや山岳スキーも可能に(下写真)。
またこれは厳密にはCord Hook™システムではないですが、おなじみのCaptureにスマートフォンケースとクリエイター キット(スマートフォンマウント)を組み合わせれば、ハンズフリーでの動画撮影も可能(下写真)。
このように、ピークデザインの他の収納やアクセサリ類との連動性することで、さまざまなアクティビティや、クリエイティブな撮影のために多彩なパッキング・携行スタイルが自由に創造することができます。これほどの斬新さ、自由度と拡張性を備えた登山用バックパックがかつてあっただろうかと思い出してみても、自分は記憶にありません。
ただ逆に言うと、それ自体でも上質な山岳向けバックパックである「アウトドアバックパック」は本質的に「ベース」であり、その真価をフルに発揮するには別売りのアクセサリーと連携させてこそ、ということでもあります。これはある意味諸刃の剣ではありますが、一方ではAppleのように計算された完璧なエコシステムがいかにユーザーにとって快適さと安心感を与えてくれるかということも皆よく知っているはず。ピークデザインがこの新作で実現しようとしていることは、まさにそれなのです。

仕分けに便利な超軽量パッキングキューブも、大きさやメッシュ・シルナイロンといった素材まで、用途に合わせて豊富にランナップ。しかもCord Hook™システムに対応しているのでバックパックに外付けも可能とどこまでもスキが無い。
背負い心地と耐久性:いずれも登山用バックパックとして高いレベル
ここまで収納について多くを語ってきましたが、もちろん登山用バックパックで重要なのは、厳しい環境下でもそのパッキングした荷物をいかに安全に、疲れないで長い時間、長い距離運べるのかということ。もちろんこれほど細部にまで計算を張り巡らすピークデザインが手を抜くはずはありません。
外装に使用されている「Terra Shell™ 210Dリップストップナイロン」は、軽量でありながら十分な引裂き強度の高さを持ち、さらに前面と底部はTPUコーティングによって特に優れた耐摩耗性と耐候性を備えています。
この面についた水滴は即座に下に流れ落ち、内部の機材を守ってくれます。個人的にも、休憩時などでザックを地面に下ろしてその上に座ったりといった手荒い使い方をしても傷ついたり汚れたりしにくいので気に入っています。登山用のバックパックとしての丈夫さは十分に備わっているといっていいでしょう。
バックパックの背負い心地を決める背面システムの作りも、専門ブランドのバックパックと比べてもまったく遜色ないばかりか、むしろこれまで背負ってきた中でもトップクラスに安定感の高い作りには驚きました。
背面には立体的コの字型で剛性と柔軟性のバランスが取れた金属製フレームが入っており、それがしっかりと腰に荷重を伝達しつつ、背中のカーブにフィットします。背面・ショルダー・ヒップベルトに配置されたパッドは重さに耐えられるようにやや硬めでありながら、クッション性と通気速乾性が確保されたフォームによって、汗による不快感も少ない作りです。
ショルダーハーネスはランニングパック由来の幅広仕様でフィット感もよく、収納性の高いメッシュポケットも便利。細かいですが、Captureをセットした時にこの幅広のおかげでCaptureの角が胸に当たることもないのがまたいい。重みが乗る部分には特に厚いパッドが配置されており、ここにフルサイズ一眼とポーチをフルにセットして歩いても肩にはそれほどの負担を感じることはありませんでした。
45Lモデルではショルダーハーネスの高さを変えて背面長を調整できるラダーシステム、そしてパックの左右へのブレを抑えるロードリフターをしっかりと備えており、体型に合わせた最適なフィット感と安定した背負い心地を可能にしてくれました。
ヒップベルトは18・25・45L全モデルで着脱可能となっており、45リットルモデルには標準で装備されています。着脱式ながら作りはしっかりとしており、重みをしっかりと受け止めつつ腰骨へのあたりも柔らかで、左右には用途の違うメッシュポケットが配置され、どちらも十分な広さを持っていて利便性も高く満足いく作りです。
ちなみにヒップベルト装着時でも背面の後ろに仕舞うことができ、TPOに合わせてスタイルを変更できるようになっていました。
まとめ:山もカメラも本気の人は迷わずチェック。決して誰も真似できない登山×カメラ×デイリーの垣根を超えたクロスオーバーな魅力
ピークデザインにとっては初のガチアウトドア向け製品ではありましたが、細部にまで妥協せず考え尽くされた完成度の高さと、ただ優等生なだけではないブランドらしさを際立たせたユニークなアイデアはさすがとしか言いようがありません。
山岳向けバックパックとしての作りの良さと実用性の高さ、先進的なデザイン性と機能美、そして何より同社のアクセサリーによって広がる多彩なアクティビティ・スタイルに対する汎用性の高さを兼ね備えたピークデザイン「アウトドア バックパック」は、平日は街で使い、週末はそのまま裏山へハイキングに出かけ、趣味の写真撮影を楽しむ、そんなライフスタイルを持つユーザーにとってこれまでなかった待望の「1点ですべてをこなす理想のバックパック」なのではないでしょうか。
確かにこのバックパックは、最高のハイキング用パックでも、最高のカメラバッグでも、ましてや最高の街歩きバッグでもないかもしれませんが、むしろその特定の分野に特化しない「ハイブリッド」な存在であるという点こそがこのバッグの最大の強みであり、唯一無二の魅力であるといえます。また重さと価格は確かに気にならないわけではありませんが、この作りの良さと他にはない魅力を考えれば納得できないものではありません。
一方で、その奥の深いシステムを使いこなすには、ある程度の慣れが必要であることも確かです。無数のストラップやパーツ類に慣れない人、あるいは必要としない人にとってはただ煩わしいだけかもしれません。またすでにピークデザインユーザーである場合はこれまでのアイテムを活用できるという意味でそれはメリットになりますが、新しくゼロから揃える場合はそのためのコストはハードルになり得ます。その意味では単なるカメラ好き、単なるアウトドア好きの人にまず最初にこれを勧めるかというとさすがに厳しいかもしれません。ただし、先ほど述べたようなアクティブなカメラ好きユーザーであれば、10年近くのピークデザイン愛用者である自分の経験から、そのコストをかける価値は十分にあると自信を持って言えます。
この無限の可能性が開けたバックパックの新しい世界は、使ってみてみないと分かりません。このレビューで興味をもたれた方はぜひ実際に背負ってみてください。
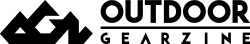
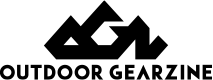


































 Black Diamond ベータライト45 バックパック レビュー:最先端軽量素材とスマートなディテールが融合した、ファストパックスタイルへのBDからの回答
Black Diamond ベータライト45 バックパック レビュー:最先端軽量素材とスマートなディテールが融合した、ファストパックスタイルへのBDからの回答 ALTRA LONE PEAK 9+ レビュー:ブランドを代表するトレイルランニングシューズが Vibram® MegaGrip をまとってフルモデルチェンジ!【実践レビュー】
ALTRA LONE PEAK 9+ レビュー:ブランドを代表するトレイルランニングシューズが Vibram® MegaGrip をまとってフルモデルチェンジ!【実践レビュー】 Review:SALOMON XA ELEVATE + OUT PEAK 20 悪路でも急斜面でも駆け抜けたい!スピードハイカーの頼りになる相棒
Review:SALOMON XA ELEVATE + OUT PEAK 20 悪路でも急斜面でも駆け抜けたい!スピードハイカーの頼りになる相棒 【所有満足度も、使い勝手も◎】JINS×Snow Peak コラボレーションアイウエア「JINS Switch Combination Titanium」を使ってみた【Quality Of Camping Life 向上委員会 #001】
【所有満足度も、使い勝手も◎】JINS×Snow Peak コラボレーションアイウエア「JINS Switch Combination Titanium」を使ってみた【Quality Of Camping Life 向上委員会 #001】