
【2025秋冬】ダウン?化繊?フリース?快適なレイヤリングのカギは素材選びから。登山向けミッドレイヤー(防寒着)のタイプ別ベスト・モデルと、失敗しない選び方のポイント
ミッドレイヤー = 防寒着?
登山やアウトドアでの服装選びを考えるとき、大切なのは「レイヤリング(重ね着)」を意識することであるといいます。
基本的には「ベース」「ミッド(ミドル・中間)」「シェル」という3レイヤー(層)で異なる機能をもった衣服を重ねて着ることを意味し、こうすることで環境変化の激しい過酷な状況でも安全・快適に行動することが可能となります。今回はそのレイヤリングのなかでも、ちょっぴり込み入った役割を担っている「ミッドレイヤー」についてまとめました。
ミッドレイヤーとはいわゆる肌着(ベースレイヤー)とアウター(シェルレイヤー)の中間に着る衣服のこと。山を登りはじめた頃は、単純に「防寒着?」くらいにしか考えていませんでしたが、ただ暖かくしてくれればそれで快適か、というとそんな簡単な話ではありません。あらゆる状況で最適な保温と快適さを作り出すためには、さまざまな要素と機能が必要になってきます。その証拠に実際のところミッドレイヤーと一言でいっても、生地の素材や形状・厚みなどによって、季節や用途、効果など最適な着方はさまざまです。
より長く山に登るようになってくると、状況によっては寒すぎたり暑すぎたり、湿気がこもったり通気性がありすぎたり、重すぎ、かさばりすぎなど、1種類のミッドレイヤーでは対処できないケースは多々出てきます。その意味でミッドレイヤーは実に奥が深い、というか、素人泣かせのやっかいな山ウェアといえます。
そこで今回は多様なシチュエーションに合わせたミッドレイヤーのベスト・モデルと、自分にピッタリの一着をチョイスするために何をどういう基準で選べばよいかということについてのポイントをご紹介します。

目次
- 【タイプ別】一度使ったら手放せない、おすすめミッドレイヤー7着
- ダウンインサレーション(春~秋):Black Diamond ディプロイダウン0.5フルジップフーディー
- ダウンインサレーション(冬):Rab Mythic G Jacket
- 保温重視の化繊インサレーション(春~秋):milestone Heatwave Titanium Hoody
- 保温重視の化繊インサレーション(冬):Rab Cirrus Ultra Hoody
- アクティブインサレーション(薄手):Arc’teryx デルタ フーディ/Rab Evolute Hoody/patagonia ナノエア・ウルトラライト・フルジップ・フーディ
- アクティブインサレーション(厚手):Teton Bros. Sub Hoody/Rab Xenair Alpine Flex Jacket
- フリースウェア(通年):Patagonia R1 エア・ジャケット
- 選び方:ミッドレイヤー(防寒着)を賢く選ぶポイント
- まとめ
【タイプ別】一度使ったら手放せない、おすすめミッドレイヤー7着
長年ミッドレイヤーの進化を見続けている筆者が、実際に愛用している現時点で「これはいい」とお墨付きをあげたいモデルを、それぞれ薄・厚手別で選んでみました。個人的な好みが多分に含まれていますので、あくまでも参考に。
ダウンインサレーション(春~秋):Black Diamond ディプロイダウン0.5フルジップフーディー
2025年時点で世界最軽量クラスのダウンフーディ(フルジップジャケット)は、冬以外にも1年を通して重宝します。1000FPの最高級グースダウンと4デニールのシェル生地を使用することで「160グラム」という驚きの軽さを実現。ダウンの強みである圧倒的な軽量コンパクトさを最大限に活かしたこのモデルは、限られた重量で最大限の暖かさを求めるあらゆる山岳愛好家の強い味方となるはず。しかもこのフルジップフーディーの他にWEB限定で「148グラム」という究極の軽さを実現したプルオーバーフーディーもあります。
最高級ダウンとはいえダウンの量は最低限なので、真冬の防寒にはならないかもしれませんが、天候による気温の変化が激しく、装備が読めない春~初冬までの登山には最高のお守りとなってくれるでしょう。
ダウンインサレーション(冬):Rab Mythic G Jacket
可能な限り軽量化したいアクティブな登山家やハイカーの要望に応えつつ、極限まで高いレベルでの断熱性を実現した、冬の本格アウトドア向けダウンジャケットのおすすめは「Rab Mythic G Jacket」。「マスターオブインサレーション(中綿の達人)」を自負するRab が到達した渾身の一作といえるこのモデルは、1000FPの嵩高性を備えた最高級品質に、極薄の7D Atmos™ナイロンリップストップ表地、そして裏地には独自の「TILTテクノロジー」によって繊維1本1本をチタンでコーティング。通気性を損なうことなく放射熱損失を大幅に低減し、熱効率を最大化しています。さっと羽織ればすぐにホカホカと暖まる保温力ながら300グラムを切る軽さで、握りこぶしほどの大きさに収納できてしまう軽量コンパクトさを持ち合わせたこのアイテムは、より重量を切り詰めることを重視するミニマリストたちが冬山でのバックパックに忍ばせておく携帯用防寒着として、間違いなく現時点でトップクラスに使える一着です。
保温重視の化繊インサレーション(春~秋):milestone Heatwave Titanium Hoody
「防寒着」という化繊インサレーション本来の役割をしっかりと果たしつつ、幅広い季節・アクティビティに活躍できる高い汎用性を備えた「万能防寒着」が、今シーズンから登場の期待のニューフェイス「milestone Heatwave Titanium Hoody」です。軽さと断熱性が高いレベルで両立したClimashield®中綿とチタンスパッタリングの裏地という、軽量ながら保温性を最大化する工夫がニクイ。ダウンと違い化繊素材だから沢登りなどの濡れになる危険がある山行でも安心です。春~秋にはしっかりと暖められる保温着として、厳しい冬には行動着としても役立ちます。
保温重視の化繊インサレーション(冬):Rab Cirrus Ultra Hoody
とにかく断熱性と耐久性重視、厳冬期の登山に持っていきたい暖かくて快適なかさ高性を備えたタフな防寒着がこちら。中綿に「PrimaLoft® ThermoPlume®」を採用し、ダウンと見間違えるほどの驚きの軽さとふんわりした着心地、そして断熱性の高さはいよいよ化繊もダウンと遜色ないレベルまで来たかと実感させるのに十分なクオリティです。その高機能中綿をふんだんに使用しながら見事な保温・通気コントロールと実用的なポケットなどを備えた「Rab Cirrus Ultra Hoody」は、Rabの技術力がいかんなく発揮された、厳冬期での防寒着として幅広く使いやすい良モデルです。コンパクトに収納できるところも冬山に最適。
アクティブインサレーション(薄手):Arc’teryx デルタ フーディ/Rab Evolute Hoody/patagonia ナノエア・ウルトラライト・フルジップ・フーディ
寒い時期でも行動着として不快感を軽減するように、通気性と汗処理能力を高めた、いわゆるアクティブインサレーションはハイキングや登山での行動着として最適。ただその中でも秋山登山などでは、そこまで厚手で(保温性が高く)なく、かといって中綿が剥き出しすぎて風がスースーでは寒いので通気性がありながら適度な防風性を備え、そして動きやすいストレッチ性を備え、なるべく薄手で軽い方がいい。そんな基準で選んだおすすめが以下。特に「Arc’teryx デルタ フーディ」のOCTAとデルタピークの組み合わせ、「Rab Evolute Hoody」のPrimaLoft Active EvolveとMotiv Aeroの組み合わせは絶妙。少し防風強めが良ければ「patagonia ナノエア・ウルトラライト・フルジップ・フーディ」も通年使えて便利。
アクティブインサレーション(厚手):Teton Bros. Sub Hoody/Rab Xenair Alpine Flex Jacket
厳冬期の雪山登山やBCスキーといった厳しい寒さで激しい発汗を伴うアクティビティでは、冷たい空気や風を防ぎつつも汗抜けの良さを両方高いレベルで兼ね備えたジャケットであることが重要。それを考慮すると、中綿は断熱性と通気速乾性が両立したアクティブインサレーションが基本ですが、適度に風を防いでくれる防風撥水性のある表生地を使っているものが理想です。さらに肩や肘周りの可動性が十分に高い優秀なモデルのおすすめは「Teton Bros. Sub Hoody」軽量・高通気・高断熱・ストレッチの中綿「ストレッチOCTA」と行動アウターとしてまんべんなく高いパフォーマンスのソフトシェル表地を合わせたモデルです。ここ数年のお気に入りで、自分はレイヤリングを考慮してフード無しタイプを着ています。
もうひとつ、甲乙つけがたくおすすめなのが「Rab Xenair Alpine Flex Jacket」。防風性と通気性、ストレッチ性を備えたPertex Quantum Air 表地にと呼吸する中綿Primaloft Gold Insulation Active+、そしてストレッチフリースのサイドパネルを採用し、細かい点まで隙がありません。風抜けの良さは上のSub Hoody に及ばないものの、逆に風や冷気を遮る性能はこちらの方が高く、寒さに強くてアウターとしてもばっちりです。
フリースウェア(通年):Patagonia R1 エア・ジャケット
パタゴニアにとってフリースは特別な存在。防寒着といえば獣毛のセーターしかなかったその昔に開発されたこの画期的な化繊の防寒着の生みの親は、40年以上にたった今でもより暖かく、より軽く、より使いやすい新しいフリースをアウトドアシーンにドロップし続けてくれています。そのパタゴニアの現在イチオシ最新フリースがR1 エア。R1シリーズといえば世界中の山岳アスリートが愛用するテクニカルフリースの代名詞ですが、その定番を大きく進化させたモデルといえます。
従来のフリースのようなある意味での「万能さ」をあえて捨てることで、寒い季節でのより強度の高いアクティビティにとって最適な通気性と保温性、そして高いレベルでの快適性を実現した、優れたテクニカルフリースでした。中空糸ジャカードフリースのユニークな構造が、軽量性と保温性、通気速乾性を高い次元で融合させています。秋冬のトレイルランニング、スキーツーリング、クライミングのアプローチ、寒い時期のハイペースなハイキングでベースレイヤーの上に着用するといった使い方で間違いなくおすすめです。
2025シーズンに初登場したフルジップジャケットタイプには、左右のジッパーポケットと胸ポケットの計3つのポケットを備え、またシルエットもスリム過ぎないので中間着としても、日常の上着としても幅広く活用できます。寒空の下でミッドレイヤーとして使ってみると、期待以上に寒い中でも暑すぎず、そして冷すぎずと快適さを維持してくれます。その保温性と通気・速乾性のバランスの良さは正直、アクティブ・インサレーションといってもよいくらいです。好みに合わせてクルーネックやフルジップ・フーディなどのバリエーションが選べます。
パタゴニアらしい上品なデザインも手伝ってトレッキング、クライミング、バックカントリー、その気になれば日常でもと、冬のあらゆるアウトドアに問題なく使える幅広さは何といっても魅力です。個人的にはこの冬オン・オフ問わず24時間手放せそうにありません。
選び方:ミッドレイヤー(防寒着)を賢く選ぶポイント
ポイント1:レイヤリングについて知る
このまま話を進めていく前に一度レイヤリングという考え方についてざっくりとおさらいしておきます(分っている方は読み飛ばしていただいて構いません)。
アウトドアでの「レイヤリング」とは、過酷な自然環境の中で少しでも安全・快適に過ごすための着こなし方のセオリーを意味しています。レイヤリングによって、主に発汗等による衣服内の水分を素早く排出し、身体をドライに保つ機能や体温を一定に保つ機能(保温)、さらに外気や雨雪からの遮断といった、1着では共存できない高度な機能を兼ね備えることができます。レイヤリングは何でもただ重ね着すればいいというわけではなく、大まかにいって以下の3つの機能をもったレイヤー(衣服)を肌面から順に重ね着することで完成します。
ベースレイヤー:汗を吸い上げ、外側に受け渡す

肌の上に直接着るレイヤーをベースレイヤーといいます。身体から出る汗を肌に残さないように吸い上げて外に逃がす(上のレイヤーに受け渡す)ことで、肌面をドライに、そして体温を一定に保ちやすくしてくれ、汗で濡れた衣服の不快感も軽減してくれます。このため生地の素材は吸湿・速乾性能の優れた化学繊維やウールが鉄板。暑い時期ならばこれ1枚で行動することが多く、年間を通じて最も着用するシーンの多い服であると言えます。
関連記事
ミッドレイヤー:保温(&湿気の排出)

ミッドレイヤーの役割は端的にいうと保温(断熱)。外部の冷気と体温との間に、中綿を詰めたウェアを挟むことによって「空気の壁」をつくります。それによって体表面近くの暖かい空気を閉じ込め、暖かさ・快適さを保ってくれます。また、ベースレイヤーから排出された湿気(水蒸気)が抜けていくだけの透湿性も重要な役割のひとつです。ただ、どんな季節やアクティビティでも常に快適な製品というものは残念ながらまだ存在しません。だからこそミッドレイヤーは賢くチョイスすることが必要なのですが、詳細についてはこのあと説明していきます。
シェルレイヤー:風・雨・雪・外気を遮断(&湿気の排出)

ベース・ミッドレイヤーが主に衣服内部を快適に保つ役割であったのに対し、シェルレイヤーの役割は主に外の環境から内部を守る役割といえます。冷気をはじめ雨・風・雪といった、快適さを脅かす可能性のある外部からの刺激を遮断し、衣服内の安全を保ちます。具体的にはGORE-TEXなどの防水透湿素材を使ったジャケットを羽織ることで、外からの風や浸水を防ぎつつ、内側の湿気を外に逃すように機能します。想定する気象条件によって、薄手の風よけ程度のものから厚手の防水・防風・断熱性の高いタイプまでさまざまです。
関連記事
ポイント2:代表的なミッドレイヤーの種類とそれぞれの特徴を知る
一通りレイヤリングの役割が分かったところで、ここからようやくミッドレイヤー選びの核心に迫っていきます。先述の通りミッドレイヤーの主な役割としては「断熱・保温」ですが、じゃあとりあえず保温性の高い上着を選べばいいかというと、これがそんなに単純な話ではありません。
山登りではじっとしている時もあれば激しく活動しているときもあるし、ちょっと肌寒い程度の時もあれば、凍てつくような寒さの時もある。すべての場面でちょうどよい快適さを提供するような1着は未だ存在していないのです。
保温が必要なあらゆる場面でちょうどよい快適さを実現するためには、さまざまな得意分野の異なる複数のミッドレイヤーを使い分けるのが、単純ですが最も賢い方法です。そのためにはまず山で着るミッドレイヤーの代表的な種類について知っておく必要があります。
代表的なミッドレイヤーその1:ダウンインサレーション

まずアウトドア用の防寒着といえば、おそらくほとんどの人がまず思い浮かぶであろう防寒着の代表格、それがダウンインサレーション(ジャケット)です。水鳥から採取される羽毛を中綿として、それを防風性に優れた表裏生地で封じ込める構造になっています。軽さに対しての断熱性にかけては世界中の素材を探してみてもいまだ右に出るものはいないでしょう。
ただし飛び抜けた断熱性の一方、加減を知らずに暖めて続けてしまうので、暑すぎて衣服内が蒸れて不快になりがちなのが弱点。また濡れてしまうと保温力は著しく低下してしまうところも注意が必要。ただ近年ではこうした弱点を克服する最新技術を駆使したダウン製品も多く現れてきてもいます。何れにせよ、極寒の場所でじっとしている時や運動量の少ない状況で暖まりたいときには間違いなく最強の防寒着です。
代表的なミッドレイヤーその2:化繊インサレーション(保温重視タイプ)

次にメジャーな中間着といえば、羽毛に代わる中綿素材として人類が開発した、主にポリエステル繊維などで人工的に作られた中綿を封入したジャケット、化繊インサレーションです。特徴は羽毛に迫る重量当たりの断熱性を備えながら、濡れに対する強さを備えていること。アウトドアでは汗や雨雪などでぐしょぐしょに濡れても保温力を失わないそのタフさは重要なメリットで、ハードなアクティビティである程、化繊インサレーションが活躍する場面が広いといえます。また洗濯しやすいという手入れの簡単さも大きな魅力。代表的な中綿素材にはシンサレート、プリマロフト、コアロフト、エクセロフトなどがあります。
どこまでいってもダウンには追いつけなかった保温性の高さも、近年では「エアロゲル」といったハイテク素材などによって着実に向上していることから、その性能・使い勝手は益々高まってきていることは間違いありません。
ちなみに厳密にいうと、最近ではウールの繊維による中綿など、ダウンでも化繊でもない中綿も現れていますが、それらは今のところこのカテゴリにまとめてしまってよいかと思います。
関連記事
代表的なミッドレイヤーその3:アクティブインサレーション(行動中着用タイプ)

もうひとつは上記の化繊インサレーションの派生製品として生まれ、ここ数年ですっかり定着してきたのが、次世代のミッドレイヤー「アクティブインサレーション」ジャケットです。
素材的にはこれまでの化繊中綿なのですが、重量当たりの保温力では上のタイプに及ばないものの、より高い速乾性と通気性を備え、万が一汗をかいても常に衣服内をドライな状態に保つような特性があります。
さらにストレッチ性を備えてよりアクティブシーンに対応しているモデルも多く、低温下で汗をかきながら激しく行動しても驚くほど快適なため、行動中でもずっと着続けていられます。
アクティブインサレーションジャケットはいわば「動ける防寒着」。冬の行動中に着っぱなしでも常に快適でいられるため、今では冬山登山はもちろん、脱ぎ着がしずらいバックカントリー等では欠かせないといえるほど便利な中間着です。
代表的な素材に、東レ 3DeFX+、Patagonia フルレンジ、Polartec® Alpha®、THE NORTH FACE Ventrix™、Primaloft® Gold Activeなど、各メーカーから続々と新素材が登場しています。
代表的なミッドレイヤーその4:フリースウェア

70年代後半、暖かいのに水分は吸わない(速乾性がある)理想の山岳用セーターとして開発され、またたく間にアウトドア向け防寒着の主役に躍り出たフリースウェアも、まだまだ私たちにとってなくてはならない存在です。
軽くて暖かく、動きやすくて速乾性があり、濡れても保温性を失わないフリースはとてもバランスの取れたアウトドア向け防寒着ですが、大勢でみると最近では他素材の猛追にあっているのが現状。ダウンに比べれば重量や収納性、保温性は劣り、またアクティブインサレーションに比べれば速乾・通気性は劣るようになってしまっているためです。
ただ長年の進化の過程で防風性を付加したものや、かさ張りを抑えたもの、よりストレッチ性を高めたものなど、技術の進歩とともに多様なニーズに合わせてさまざまなフリースが誕生し続けており、まだまだ終わったものとして片付けるには惜しい存在です。
ポイント3:着るタイミングとシチュエーションに合わせる
以下に先ほど挙げた代表的なミッドレイヤーと一般的な特徴の比較を表にまとめてみました。
もちろん個々の製品の個性や生地の厚み、中綿の質・量によって性能は大きく上下するので、あくまでも目安として考えてください。
| 種類 | ダウンインサレーション | 化繊インサレーション(保温重視タイプ) | アクティブインサレーション(行動中着用タイプ) | フリースウェア |
|---|---|---|---|---|
| 保温素材 | ダウン | 化学繊維など | 化学繊維 | 化学繊維 |
| 重量当たりの断熱性 | ◎ | ◯ | △ | ◯ |
| コンパクトさ | ◎ | ◯ | ◯ | △ |
| 通気性・速乾性 | × | △ | ◎ | ◯ |
| 濡れに対する強さ | × | ◎ | ◯ | ◎ |
| 着心地の良さ | ◎ | ◯ | △ | ◎ |
| 動きやすさ | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
| 防風性 | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 手入れの簡単さ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
上の比較表を参考にすることで、自分が求めている防寒着の種類を絞り込むことができます。ここで分かるように、それぞれの防寒着は機能的には大きく言って相互補完的になっており、どれか1つですべてOKというものではありません。このため最高の安全と快適さを得るにはシーンによって使い分けることができるのがベストであり、常にダウンジャケットとアクティブインサレーションを2つ持っていくことが現時点では最高の選択と言えます。ただもちろん予算や物理的な関係でそれが毎回できるという保証はなく、それぞれのコースによって重視することを見極め、着用・携行するウェアを選択することが重要です。アウトドアの道具選びはそこが難しいところであり、楽しいところでもあるわけです。
とはいえ、もっと簡単に答えが知りたいという方のために、少し乱暴ではありますが最適なミッドレイヤーを選ぶための質問を以下の2つにまとめてみました。もちろん、各カテゴリでも多くの機能を兼ね備えた万能モデルが存在していますので、一概には線引できないことはご留意ください。
質問その1:着るタイミングは?
まず最初にする質問は、その中間着を「止まっているとき(じっとしているとき)に着るのか、それとも行動中にも着るのか」ということです。
自分は防寒着を着るときには動かない(汗をかかない)ということが前提の人には、「ダウンインサレーション」か「化繊インサレーション(保温重視タイプ)」の二択になります。一方冬のアウトドアなどで止まってても動いてても肌寒い、だから行動中にも着ていたいという場合には、「アクティブインサレーション(行動中着用タイプ)」か「フリースウェア」の二択です。
質問その2:着用時の不安要素は?
止まっているときに活躍するミッドレイヤーを選んだ場合、その際次に考えるべき質問は「濡れの心配が少ないケースでの着用なのか、濡れる心配もある山行で着るのか」です。それぞれによって、以下のような種類が導き出されます。
| 止まっているときに着る | |
|---|---|
| 濡れの心配は少ない | ダウンインサレーション |
| 濡れる可能性がある | 化繊インサレーション(保温重視タイプ) |
行動中に着て活躍するミッドレイヤーを選んだ場合、ここからは微妙な差異ですが、より通気・速乾性を重視するのか、もしくはバランスや着心地を重視するのかを気にするといいでしょう。それぞれで以下のようなタイプを選ぶことがおすすめです。
| 行動中も着る | |
|---|---|
| 激しく汗をかく | アクティブインサレーション |
| 汗はそこそこ | フリースウェア |

ポイント4:その他にチェックしておきたい防寒着選びの重要ポイント
個人的にこれまでの経験から、中間着を選ぶ際に注意しておいた方がいいポイントは以下。
ポケット
アウターとして使う場合には左右のハンドウォーマーポケットがあると便利だが、中間着として中に着るのであれば不要。むしろその時は胸ポケットが便利。
フード
フードのあるなしで頭まで防寒できるかできないかという違いが出てきます。当然単体で考えればフードがあった方が防寒力は向上すると考えてよいのですが、ここはできればレイヤリング全体で考えた方がよいでしょう。例えばベースレイヤーにもフード、ミッドレイヤーにもフード、そしてアウターにもフードが付いていた場合、それはそれで結構首周りが大渋滞を起こしてしまい、逆に暑苦しい、かさばって息苦しいといったことになってしまうからです。最低限アウターにフードがあって、バラクラバなどで首元が保温できればそれで充分と考えることもできます。その場合は中間着はフード無しのジャケットで十分です。実際ぼくはそのパターンが結構気に入っています。
ストレッチ素材で頭のサイズにフィットするようになっているもの、もしくはドローコードで調節できるものが主流。そのどちらでもないパターンでは、自分のサイズに合っていないと被ったときに空気が漏れる・視界が遮られるなどで不快です。またアウター前提の防寒着の場合、ヘルメットの上から被ることを想定して大きめに作られている場合が多いので、その辺は好みが分かれるでしょう。
表生地(アウターとして着るかどうか)
山でのレイヤリングにおいては、基本的に防寒着はシェルの下に着る中間着として考えられていますが、セーターやフリースのように断熱素材のみで構成されている服の場合は軽くて通気性が高く汗抜けしやすい分、山でアウターとしては使いにくいというデメリットがあります。一方防風・撥水性等を備えたシェル生地で中綿を挟み込んだタイプはアウターとしても利用可能ですが、中間着として使うと通気性といった面でシェル生地1枚分の無駄が生じてしまいます。どちらが優れているということではなく、用途に合わせて使い分けられるのがベスト。
まとめ
ミッドレイヤーの選び方について自分なりのベストチョイスを考えてみました。もちろんこれはあくまでも理想型であり、限られた装備の中で工夫して自分のスタイルをつくるのが愉しいし、大切なのは言うまでもありません。「不快=危険」なアウトドアでは、例えば予想外の吹雪が適切な着こなしで素晴らしい体験になることも、間違った着こなしのために二度と味わいたくない恐怖の体験になることも紙一重であることを忘れずに、みなさんにとって理想のミッドレイヤーにめぐり逢えれば幸いです。
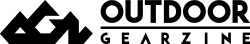
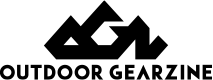










 【2025秋冬】厳しい雪山に不可欠なハードシェルジャケットの今シーズンベスト・モデルと、失敗しない選び方のポイント
【2025秋冬】厳しい雪山に不可欠なハードシェルジャケットの今シーズンベスト・モデルと、失敗しない選び方のポイント 【2025秋冬】秋冬アウトドアに欠かせない化繊インサレーション約200モデルから選んだ、用途・こだわり別ベストモデルと失敗しない選び方のポイント
【2025秋冬】秋冬アウトドアに欠かせない化繊インサレーション約200モデルから選んだ、用途・こだわり別ベストモデルと失敗しない選び方のポイント 【2025秋冬】200着以上を比べて選んだ今シーズンの季節・目的別おすすめベースレイヤーと、自分に合った最適な一着の選び方
【2025秋冬】200着以上を比べて選んだ今シーズンの季節・目的別おすすめベースレイヤーと、自分に合った最適な一着の選び方 比較レビュー:この冬着てみて分かった、化繊インサレーションジャケットのベストチョイス
比較レビュー:この冬着てみて分かった、化繊インサレーションジャケットのベストチョイス