
【2025秋冬】厳しい雪山に不可欠なハードシェルジャケットの今シーズンベスト・モデルと、失敗しない選び方のポイント
ハードシェルとは登山をはじめとした冬のアウトドアで着るウェアのなかで最も外側に羽織るアウタージャケット。端的にいうと「雪山や氷壁を対象にした登山・山岳スキーを念頭に置いて作られているアウター」です。実際のところ、雪山でも気象・積雪条件によっては厚手のレインウェアでも十分な場合もあります。ただ厳しい寒さや過酷なルートになると、どうしても生地の耐候性や強靭さが物足りなくなってきますので、より雪山を想定した丈夫な生地と細部の作りを備えたハードシェルがやはり安心です。
そこで今回は、冬のアウトドア・アクティビティに最適なハードシェルについて、編集部が自信をもっておすすめできるハードシェルジャケットの「用途・こだわり別のおすすめモデル」を紹介し、後半ではハードシェルジャケットを賢く選ぶために気をつけるべきポイントにについてまとめてみます。
なお、ここでは各部門で1着ないし2着しか紹介していませんが、その他のベスト候補やそれらを含めた全144着の比較一覧表はメンバーシップになっていただくことで閲覧することができます。
Outdoor Gearzineのコンテンツは、みなさんのご支援によって支えられています。ご興味のある方はぜひこれを機会にメンバーシップの加入をご検討ください!
すべてのおすすめハードシェルジャケットと全144モデルの比較一覧表は有料メンバーシップで
今シーズンのハードシェル市場動向の印象
今回も例によって2025-26シーズンに日本で販売されている(一部日本では正規販売していないものもアリ)アイテムをできる限りくまなくチェックしてみました。その数約150モデル。
限度を越えつつある高すぎる価格帯
リストアップしてみての第一印象は予想通り「高い」。
コロナ禍前までならそこそこのモデルを買おうとした場合、高くても8万台程度だったのが、今では軒並み10万越えが当たり前。僕が2015年にアークのアルファSVを購入した時の価格は8万6千円、それが今年のモデルは15万円とほぼ倍ですよ(それで収入も倍になっていれば問題ないですが……)。
原料供給不足、インフレ、関税、円安と、考え得るあらゆる上昇圧力が総力を挙げてモノの値段を上げにかかってる感じです。残念ながら今の雪山には体力だけではなく経済力まで必要になってしまっているのが現状です。
それでも3万円台から買えるありがたいモデルもわずかですがちゃんとあるのが救いです。今回はそんな低価格モデルもたくさんピックアップしているので、お財布に優しい優秀モデルは後ほど紹介します。
各ブランドからPFASフリーのGORE-TEX PRO ePE メンブレン採用モデルが本格的に出そろった
次に今シーズンの大きなトピックとしては、「PFASフリーのGORE-TEX PRO」製品が各ブランドから出揃ったことでしょう。
ここ数年、PFASフリー素材への移行に伴ってGORE-TEX PRO ファブリックを用いたハードシェルが極端に少なくなっていましたが、今年になってようやく各ブランドからまた新作が登場し始めましたみたいです。
その優れた耐久性、透湿性から、やはり冬山登山という極限状況ではまだまだ最も信頼のおける生地のひとつであることに疑いの余地はありません。まだしっかりと試していませんが、より軽くしなやかになったメンブレンによって着心地はよくなっているらしいので楽しみ。
ただ気がかりなのはやはり新しいPFASフリーDWR加工による撥水性能の低下で、こればかりはまだ決定的なテクノロジーのジャンプがない以上、正直期待はしていません。そこで今年は、アウトドア製品専門の宅配クリーニング店として一部にはおなじみの「洗匠屋」が販売し始めた「フッ素系のアウトドア衣類向け撥水剤」を自分で購入してみたので、今度それを使って撥水性がアップするかどうか、実験してみたいと思います。
非GORE-TEXモデルも侮れない。GORE-TEXにはない生地のストレッチ性と撥水性、通気性、コストパフォーマンスなどに注目
GORE-TEX PRO(あるいはその下位モデルのGORE-TEX 3L)が優秀な分、どうしても今年の雪山向けハードシェル選びでは第一候補になってきてしまうのですが、その他の独自生地も決して負けてない。
特に現在のGORE-TEX製品にはない「ストレッチ性」「撥水性能」「コストパフォーマンス」に優れたモデルには注目です。
数年前のアップデートで一度誕生した「GORE‑TEX PRO stretch technology」ですが、PFASフリーへの移行でいつの間にか消滅してしまいました。またGORE-TEXモデル(をはじめとしたPFASフリーDWR製品)は先ほど書いたように撥水力がまだ低く、さらにGORE-TEX製品はどうしてもそれなりに高額になってしまうという弱点があります。
それらの点では独自生地採用にも勝機はあります。例えばTeton Bros.と東レの共同開発素材である「Tasma」は、事実ストレッチ性と通気性というGORE-TEXにはない機能を備え、既存の(環境負荷的には懸念がゼロではないにしても撥水力は高い)C6撥水加工を採用し、なおかつ価格も抑えるなど、GORE-TEXモデルにはない特徴をもった生地であり、そのメリットを活かしたジャケットは半端なGORE-TEX PROモデルと比較しても十分に魅力的です。その意味では、用途や条件によっては決して「GORE-TEX」一択という状況ではありません。
用途・こだわり別ベスト・ハードシェル
1.オールラウンドハードシェル
はじめにハードシェルはその構造からざっくりと大きく「アルパイン系」「スキー系」、そしてその中間的なつくりの「オールラウンド系」に分けることができます。もちろんその中でもそれぞれでグラデーションはありますが、購入にあたってはだいたいこの3分類に振り分けられると考えていれば間違いはないでしょう。
その中でオールラウンド系は無難で一番守備範囲が広いモデルで、全体的なバランスの良さが魅力の一着です。
ハードシェルとしての基本的な性能は高いレベルでありつつ、他の分類と異なる点は、
- 長すぎず短くすぎない丈
- スリムすぎずダボダボ過ぎないシルエット
- 多すぎず少なすぎないポケット類
といったところでしょうか。
各ブランドを代表する定番・ロングセラーモデルが多く、まだ明確に目的が絞り切れないビギナーから、これ一着ですべてをこなしたいと考える人まで幅広い人にもおすすめできるモデルということができます。
その中であえて1つ選ぶとしたら「Rab Latok Mountain GTX Jacket」。最新のGORE-TEX PROを80Dと40Dで使い分けることで軽量性と耐久性を高いレベルで実現。安心の動きやすさを提供する立体裁断パターン、そして胸・左右・内ポケットと収納もぬかりなく、隙が無い。
2.オールラウンド軽量ハードシェル
上記のオールラウンド系の特徴を備えたモデルの中でも特に軽量なモデルを考えました。雪の上でもライト&ファストスタイルでいきたい方向けです。
基準としては、オールラウンド系の特徴を備えつつ
- 重量400グラム以下
のモデル。
ここで注目した一着は「MONTURA MAGICA GTX PRO JACKET」。なんと昨年撤退したかと思われたMONTURAがこんなにもすぐに帰ってくるなんて!なんでも今度は「モントゥーラ」と呼ぶらしいよ。
こちらの一着は最新鋭のしなやかなGORE-TEX PROを使い、極限まで重量を切り詰めることでなんと300(330?)グラムという驚きの重量を実現。ポケットも脇下ピットジップもついているのに。さすがに厳冬期の冬山はおすすめしませんが、スノートレッキングからスキーツーリングまで、ハイテンポな幅広いアクティビティに使えそう。
3.オールラウンド低価格ハードシェル
オールラウンド系の特徴を持ちつつ、しかも価格がほぼ5万円を切るモデルという縛りで選んでみたのがこの部門。
ここでの一押しは「MILLET ティフォン ウォーム ネクスト ストレッチ ジャケット」を挙げてみたい。耐久性のあるナイロン生地を使い、耐水圧と透湿性もトップクラスのスペックをもち、ストレッチ性まで備えた高品質生地を使用。つくりもしっかりと雪山登山に対応しながら、価格は4万切りと良心的。
4.オールラウンド低価格・軽量ハードシェル
オールラウンド系かつ軽量(500g以下)、それでいて価格がほぼ5万円を切るモデルという縛りでは「finetrack エバーブレス プリモ」がおもしろい。
何より高い防水透湿性とストレッチ性を備えたエバーブレス生地が秀逸で、それ以外でも日本の冬山を知り尽くしたメーカーによって、細部まできちんと作りこまれています。
さすがにこれ一着で厳冬期のアルプスまで万全とはいかないまでも、ハードシェル一着目としては十分に役割を全うしてくれるでしょう。
5.高プロテクション・高耐久ハードシェル
厳冬期の冬山を長期で縦走したり、過酷な状況に耐えなければならないバリエーションルートなど、とにかく対候性と堅牢性、耐久性を最優先したモデルでの注目モデルはこちら。特徴としては、基本はオールラウンドかアルパイン系の構造で、その上で、
- 厳しい寒さに耐える防寒性
- 雨や風雪にも強い対候性
- ちょっとやそっとでは壊れない丈夫な生地
が最優先。そんな条件での注目の一着といえばやはり永遠のミスター・タフ・ジャケット「Arc’teryx アルファ SV ジャケット」です。アークの中でも最も優れた耐久性と防水通気性を備えた100Dナイロンの高耐久生地を採用しながら軽量性にも優れたた本モデルは、あらゆる部分で最先端の技術が詰め込まれた、まさにアークテリクスの象徴ともいえるモデル。
6.アルパイン向けハードシェル
アイスクライミングや冬期バリエーションルートなどのクライミング系アクティビティでの快適性をより重視した分類がこの「アルパイン向け」。もちろんこれまでのオールラウンド系でも無理ではないが、クライミング時には、シビアな場面になればなるほど快適性が全然違ってくる。
何が違うかというと、主な特徴としては、
- 擦れやバタつきを防ぐための、身体のラインに沿ったスリムなシルエット
- 腕の振りなど上半身の大きな動きでもストレスのない機動性
- ヘルメットの上から被る前提でのフィット感と対候性の高いフード
- ハーネスを着用している前提での細かな配慮
でしょうか。
ここでのおすすめは、どれも甲乙つけがたく一着に絞るのがかなり難しかったが「Patagonia プルマ・プロ・ジャケット」を挙げてみたい。理由は生地がGORE-TEX PRO 80Dと耐久性ばっちり。スリムで動きやすい立体裁断と完ぺきなフィット感のフード、そして胸・左右・内ポケットのぬかりない収納と、アルパイン・ハードシェルとして頭一つ抜け出た完成度だから。でも他のモデルも決して明確に劣っているわけではないので、好きに選んでほしい。

7.アルパイン向け軽量ハードシェル
クライミング向けの中でも特に重量を削って軽さを前面に押し出したモデルは、ちょっとしたことで簡単に破れる可能性があるので万人にはおすすめできないのですが、それでも軽さと動きやすさを最優先したいという
人のための一着を選んでみます。
この中では「Arc’teryx アルファ ジャケット」が軽い中でも総合力の高さで一押しです。20Dと40Dいう驚きの薄さのナイロンを使いながら、超高耐久の50D Hadron™リップストップ素材をブレンドすることで軽量ながら高い引き裂き強度を実現。安定の立体裁断もアルパインジャケットとして申し分なし。
8.アルパイン向け低価格ハードシェル
アルパイン系の中でもコストパフォーマンスの高いモデルは、文句なしで「mont-bell ストリームパーカ」がやばい。ここで出てきたおなじみモンベルの2025年最新モデルは、独自の高透湿・ストレッチ3層生地の「スーパードライテック」を採用し、軽量ながら適度な耐久性も備えています。さらに冬期登山をストレスなくこなすだけの十分な機能性もまんべんなく備え、それでいて価格は驚きの3万円台前半。お財布が苦しい人でもこれなら納得。
9.オールラウンド・バックカントリー向けハードシェル
最後の分類はゲレンデスキー・サイドカントリー・フリーライド・バックカントリースキー / スノーボードなど、山岳スキーに特化したハードシェル。主な特徴はハードシェルの基本的な機能の他、
- 長めの丈やゆったり目のシルエットなど、レイヤリングとスタイルを意識した裁断
- 深雪の侵入を防ぐパウダースカート
- 大き目のヘルメットも想定したフード
- リフト券ポケットやゴーグル、グローブ、クライミングスキンなどを想定した豊富な収納
- 効果的なベンチレーションやゴーグルワイパーなど、アクティビティに特化した実用機能
などがまっさきに挙げられます。
で、そんなバックカントリー向けの中でもまずは滑りも登りもゲレンデも、まんべんなく対応してくれるオールラウンド系です。
ここも優秀なモデルがたくさんあるのでひとつに絞るのは容易ではありませんでしたが、個人的な好みも含めて選ばせてもらうと、まだ今シーズンもやはり「Teton Bros. TB Jacket」でしょうか。
ここまで低価格モデル以外はほとんどGORE-TEX系のモデルでしたが、Teton Bros.の誇る「Tasma」は適度に抜ける通気性からしなやかさ、ストレッチ性、そして耐久撥水性まで素晴らしいパフォーマンスで、使い始めて3年ほどになりますが極寒の厳冬期でないかぎりまったく不満がありません。
他にもダボつかず適度なゆとりのある動きやすいシルエット、喚起しやすいベンチレーション、扱いやすい袖口のベルクロなど、細かい部分まで好きな点が多すぎです(唯一あるとしたらフードの作りはもう少し上手くできる余地があるか)。
なかなかこれを超えるBCスキージャケットが出てきてくれないことはうれしくあり悩ましくもあり。

ただ今シーズンはGORE-TEX PROの逆襲が始まるわけで、このまま安泰という訳にもいかないでしょう。特に数年ぶりに復活する「Patagonia パウスレイヤー・ジャケット」は今のところ生地も見た目もポケット類も理想に近いスペックなので、ひそかに期待しています。
10.フリーライド向けハードシェル
パウダースノーを攻めたいけど、別に登山口からフルハイクはしない。やってもリフトトップから数十分ハイクアップする程度という、特に滑りに特化したい人にとっては汗処理性能はそんなに必要なし。代わりにゲレンデでの利便性と滑りの快適性、スタイルの良さが重要でしょう。そんな人にはこのモデル「PeakPerformance M バーティカル ゴアテックス プロ ジャケット」はいかがでしょう。ゆったりシルエットとやや重すぎなことで軽快な山岳スキーには向いていませんが、ニセコや八方、かぐら、谷川岳など、ゲレンデのサイドカントリーを楽しみながら、時に足を延ばしてバフバフのパウダーを落とすといったスタイルにはもってこいです。
11.スキーツーリング向け軽量ハードシェル
そもそも山岳スキーというのは、雪山を足の代わりにスキーを履いて登るアクティビティであり、その意味ではゲレンデからアクセスするなんて邪道っす。どちらかというと自分はこっち派、なんてうるさ方しぐさは置いておいて……つまりは「がっつり長い距離登ってサッと降りる」ツーリングスタイル重視のバックカントリーに適したハードシェルです。
それはフリーライド向けとは真逆の特徴、すなわち、
- 必要最低限の機能と生地厚で極限まで重量を切り詰め
- 汗や蒸れの処理に長け
- 軽快さを最優先にしたスリムで動きやすいパターン
を重視しています。
この種の「軽快BC」タイプのハードシェルではぜひとも「NORRONA lyngen Gore-Tex Jacket」がおすすめ。なんといっても362グラムという軽量仕様に加えて、スリムながら動きやすいシルエット、軽さと耐久性を両立した3層GORE-TEXは裏地にC-knitバッカーを採用してしなやかで着心地も抜群。2つの胸ポケットもちゃんとあるし、脇下のベンチレーションは動きを妨げるので排しつつ、代わりに前面に大きく設けるなどよく考えられています。スリムなシルエットなので、重ね着を考えたサイズ選びに注意しましょう。
12.バックカントリー向け低価格ハードシェル
最後にバックカントリータイプのハードシェルでの低価格モデルをチェックして終えようと思います。
オーバー気味のシルエット、豊富なポケット、深雪へのプロテクション、ヘルメットやグローブ対応のフード・袖口など山岳スキーに対応した特徴を備えつつ、価格が控え目のモデルはかなり稀少で、最低限納得できる機能性を有したモデルはどうしても5万円以上を覚悟しなければなりませんでした(モンベルを除いてw)。ただそんな中でも相対的にお買い得だなと思ったのが「Rab Khroma Kinetic Jacket」です。ソフトシェルのようなしなやかな生地でも耐水圧20000㎜、透湿度25000gと高スペック。緻密な立体裁断と高いストレッチ性で動きやすく、ポケット類も外側3つ、内側2つで十分です。これで6万円ならば、この物価高の世の中では決して高くはないといえるでしょう。
失敗しないハードシェルジャケット選びで大切な5つのポイント
ハードシェルとは
雪山にハードシェルが欠かせない理由を一言で言うと、最も過酷な積雪期の冬山で最高のパフォーマンスを発揮するために最新の技術が投入され、雨だけでなく風雪を含めたあらゆる天候に適応できるような防水・防風・耐久・通気・透湿性を備えているからです。
積雪期の雪山でも天気が良ければ太陽の温もりを感じ、ポカポカした中で気持ちよく行動できることもありますが、天候が悪化すると一変、吹雪になり、暴風雪が襲いかかってくることもあります。そんな時に暴風雪から守ってくれるのがハードシェルです。
ただ、アウトドアショップに行ってみるとハードシェル以外にもソフトシェル、レインウェアなど、アウターとして着用できるジャケットの種類は豊富にあることに気がつくはずです。ぱっと見た限りではレインウェアと何が違うのか、よく分からない場合もありますよね。それぞれの違いはなんなのか?そんな疑問に思う人もいるはず。
まずハードシェルが冬のアウトドア・アクティビティには欠かせない理由を、他のシェルレイヤーやレインウェアとの特徴を比較してみることで確認してみましょう。
ハードシェル・ソフトシェル・レインウェアの特徴の違い
ハードシェルは雪山アクティビティでのマストアイテム
| 種類 | ハードシェル | レインウェア | ソフトシェル |
|---|---|---|---|
| 防水性 | ◎ | ◎ | ◯ |
| 防風性 | ◎ | ◎ | ◯ |
| 防寒性 | ◎ | ◯ | ◯ |
| 透湿性(通気性) | ◯ | ◯ | ◎ |
| 耐久性 | ◎ | ◯ | ◯ |
| ストレッチ性 | △ | △ | ◎ |
| 重量 | ◯ | ◎ | △ |
| ざっくりとした生地の質感 | ザラザラ | ツルツル | しっとり滑らか |
| 袖口 | グローブを着用を前提とした広口可変構造 | 素手での利用を前提とした可変構造 | 素手での利用を前提とした可変構造 |
| フード | ヘルメット着用が前提で調節可能 | ヘルメット対応・非対応両モデルあり | ヘルメット対応・非対応両モデルあり |
| ベンチレーション | ついているモデルがほとんどで、大きく開くものが多い | 有り・無しの両モデルあり | ついていないのが基本 |
ハードシェルには防水・防風・透湿の機能が備わり、過酷な環境に耐えうる強度のあるウェアですが、他にも冷気をシャットアウトする襟やフードの構造、雪面滑落時の摩擦抵抗や撥水性能を高めるザラッとした質感の表生地、グローブ着用を想定した袖・裾など、雪山で快適に使用するためのさまざまな細かい機能や工夫が凝らされています。
季節やアクティビティによっては生地のしっかりしたレインウェアでも代用できる場合もありますが、本格的な雪山登山を考えている人や、BC(バックカントリー)スキー / スノーボードをする人にとって、ハードシェルは頼りになるマストアイテムといえるでしょう。
ハードシェルジャケット選びで大切なポイント1:用途に応じたタイプを選ぶ
ハードシェルジャケットを選ぶ際、まず初めに用途を決める必要があります。ハードシェルジャケットにはアルパインクライミング向けに作られているものや、BCスキー/スノーボード向けに作られているジャケットによって微妙にサイジングや機能、デザインが変わってきます。
- アルパインクライミング向け・・・上半身の動きやすさ重視で細身のフィットで、ハーネスなどの登攀具を付けることを想定したデザイン
- 山スキー/スノーボード向け・・・ややゆったりめのフィット(中により厚手の防寒着を着込めるように)で、滑走中に雪が入りにくい構造
登攀系の冬山やアイスクライミング用に考えているのであれば、ゆとりのあるフィット感のウェアではハーネスなどを装着した際に邪魔になってしまいますから、スリムフィットのウェアをチョイスするのがセオリー。ハーネスをつけることで腹部のポケットも使えないことがあるのでポケットの位置などもしっかりとチェックしたいところです。
山スキーやスノーボードなどは滑走中の動作が大きくなるため、ゆったりめで、着丈の長いタイプの方が滑走中に雪が入りにくく、動きやすいでしょう。ゲレンデでの滑走時はリフトに乗っている間は寒いため、ウェアの重ね着を想定して選ぶと失敗しにくくなります。
ハードシェルジャケットは明確に◯◯用、◯◯用と線引きされているわけではないため、アルパインクライミング向けのウェアでスノーボードができないわけではなく、(逆も然り)あくまで適したデザインになっているだけですが、用途を決めておくことでハードシェルジャケットは選びやすくなります。
ハードシェルジャケット選びで大切なポイント2:防水透湿性能の生地・素材を選ぶ

ハードシェルジャケットは行動中常に着用していることが前提のため、晴れているときも雪や雨の時も常に快適でいられるよう、あらゆる天候で快適な防水透湿素材の生地が使われています。当然ながら、生地の防水性・透湿性が高ければ高いほど品質の高いウェアと言えるでしょう。
さまざまな防水透湿生地の中でも、GORE-TEXは数十年にわたって多くのアウトドアメーカーが採用している素材です。高い防風性・透湿性・耐水性を備え、すべての製品でラボや実際のフィールドでの厳しいテストを実施して作られています。その意味であらゆるタフなアクティビティにおいても安心して使うことのできる素材です。
中でも最も過酷な条件で使用することが想定されたハイエンドラインである「GORE-TEX PRO」は、耐久性のある表・裏地に、十分な防風・撥水性、激しい発汗にも対応する優れた透湿性を備え、冬山でのあらゆるタフなアクティビティで、安心と快適さを提供してくれます。もちろんGORE-TEXの他の種類でもハードシェルはありますが、もし厳冬期の冬山までを考えているのであればGORE-TEX PROがおすすめです。
用途と目的が決まっていて、価格帯も考慮するならばメーカー独自素材も十分アリ
一方でGORE-TEX以外で、各メーカーが独自で開発している防水透湿素材も日々進化しており、最近では王者GORE-TEXに負けず劣らずの高性能素材も存在していることにも注目です。これらの素材は総合力ではなく、透湿性や重量、着心地など、特定の部分でGORE-TEXより優れていることが多く、さらにうれしいことにGORE-TEXよりもやや低く抑えられた価格帯であることが多いのが特徴。
有名どころをかいつまんで紹介すると、パタゴニア独自の防水透湿素材「H2Noパフォーマンス・スタンダード・シェル」、モンベルの「スーパードライテック®」、ノースフェイスが開発した「FUTURELIGHT™(フューチャーライト)」、マウンテンハードウェアの「DRY Q(ドライQ)」、ティートンブロスが東レと共同開発した「Täsmä(タズマ)」などなど。
これまで積み上げてきた実績でGORE-TEXにかなう素材はないとはいえ、個々の特徴や価格など、ある面でGORE-TEXより優れた素材はたくさんあります。基本的な防水透湿性能をクリアしたうえで、用途と使用環境・価格帯に合わせて無駄のない生地・素材を選びましょう。
ハードシェルジャケット選びで大切なポイント3:生地の厚み(耐久性)と重量とのバランスを考える

過酷な環境下において、必要な道具を全て背負い行うアウトドアアクティビティでは、重量や耐久性も重要になってきます。
常に着用するハードウェアジャケットですが、重ければ行動時にかかる負担が大きくなり、動きにくさからストレスを感じるでしょう。
衣食住を全て背負い、長距離を歩くようなシーンではできるだけ重量が軽いウェアを選ぶべきですし、BCスキー(スノーボード)において、ツリーランなどする際や、岩と雪のミックスされた険しい場所を登攀するようなシーンでは小枝にひっかかっても切れず、岩に擦っても穴の空かない耐久性が求められます。
ハードシェルジャケットの重量は使用されている「糸」の太さや生地のレイヤー(何層)なのかや、付帯機能(ポケットなど)によって変わってきます。一般的に太い糸を使用したジャケットはその分重たくなるし、防水のために使用しているシームテープなども影響してきます。
生地の厚さは使う「糸」によって差が生まれますが、糸の太さ=耐久性というとそうではありません。
例えば、シンプルに考えれば40デニールの糸を使用したウェアよりも80デニールの糸を使用したウェアの方が生地は厚く重たい反面、耐久性が高くできるといえますが、細くても密に編めば強度は上がるし、重量も上がるため糸の太さと耐久性は一概に相関関係にないことが分かりました。
使用している糸の太さや、縫製の密度までなってしまうと、公表しているメーカーは少ないので、実際には試着し、着心地や、着用時の重量感など確かめましょう。
ざっくり50着ほどのウェアの重量を確かめてみたところ、アルパインクライミング向けのハードシェルジャケットでは平均すると500g〜600gほどで、500gを切るウェアは軽量な部類と言え、600gを超えてくると重たいとウェアと言えそうです。
BCスキー向けのウェアとなると、スノースカートや大きめのポケットがあるモデルが多いため、アルパインクライミング向けに比べ重く、600g台が一般的です。
ハードシェルジャケット選びで大切なポイント4:必要な機能が備わっているか確認する
用途によって求められる機能も変わってきます。
それぞれのウェアに備わっている機能は最終的に使いやすさと着心地に大きく影響してきます。ハードシェルジャケット選びを失敗しないためには必要に応じた機能が備わっているかも購入前にしっかりと確認しましょう。
購入前にチェックしておきたいパーツ・機能
- フロントジッパー
- ポケット
- フード
- スノースカート
- ベンチレーション
- 襟
ジッパー:開閉のしやすさや防水性をチェック

ジッパーにもさまざまな種類があり、使いやすさを左右する重要なパーツです。
ジッパーは防水性が高いものを使っているか。また開閉のしやすさも重要です。止水ジッパーのタイプによっては硬く、片手では開け閉めできないモデルもあるので要注意。脱ぎ着するためのメインジッパーだけでなく、ベンチレーションやポケットのジッパーもしっかりと確認しましょう。
壊れにくく、凍結しにくく、防水性も高くて軽量なビスロンタイプの止水ジッパーは、冬山用に多く採用されている信頼性の高いジッパーです(下写真)。
開閉のしやすさだけでなく、ダブルジッパーになっているモデルなら、ジャケットがバタつくことを防ぎつつも効果的に換気を行うことができるので便利。ジッパーはグローブを装着した状態で開閉がしやすいかもチェックしましょう。
ポケット:用途に合わせて配置・数が違うため、行動時のアクセスしやすさをチェック

胸ポケットがあるとスマホなど入れておくのに便利
ポケットは数が多ければいいってことでもありません。どこに配置されているのかも重要です。アルパインクライミング向けのウェアはハーネスを取り付けることを想定し、腹部をポケットは廃し、代わりに胸ポケットが大きく、両サイドに設けられているモデルもあります。
BCスキー(スノーボード)向けのウェアであれば、胸ポケットは小さめで、代わりに内ポケットにゴーグルやスノーグローブ、シールなどが入るほど大きなポケットが用意されていることが多いです(これあると便利です)腕にポケットがあるモデルも多く、ICチップを採用しているゲレンデではゲートの通過がストレスなく行えます。

鍵などの貴重品はアクセスの頻度の低い内ポケットに入れておくのがおすすめ。内ポケットのないウェアもありますので注意が必要です。
フード:アジャスターを使った時のフィット感をチェック

悪天候の時にはフードはマスト。大きさもメーカーによっては千差万別。フィット感はしっかりとチェックしましょう。
フードにツバが付いていないモデルだと雨や雪が降っている時に顔の露出した部分が濡れやすくなります。ツバの長さは好みにもよりますが、長い方がよりガード力が上がりおすすめです。
基本的にヘルメットの上から被れるよう大きめの設計になってるモデルが多いですが、フードが大きすぎるとヘルメットなしではうまくフィットしないこともあります。アジャスターが設けられているため、ヘルメット無しでのフィット感を確認しましょう。

アジャスターでフィット感を確認
フードにアジャスターがついていても、サイズが合わないと横を向いた時に視界をさえぎってしまうこともありますから試着の際には顔を左右に振ってみて視界が確保できるか確かめましょう。
スノースカート:雪の侵入をシャットアウト

ハードシェルの中に雪が入り込むのを防いでくれるスノースカート。BCスキー(スノーボード)などを目的としたウェアには装備されていることが多いです。なくてもそこまで酷いことになったことはありませんが、パウダーランをするようなシーンで、雪の侵入をしっかりとプロテクトしたい時はあると便利です。転倒した時に雪の侵入を防いでくれるので、BCスキー初心者はスノースカートのあるウェアを選ぶ方がいいでしょう。
一方アイスクライミングなど垂直方向の雪山登山で主に使用する場合には、スノースカートは重くなるだけで不要、という場合の方が多いはず。その場合は逆にスノースカートがないか、あるいは取り外しが可能なモデルを選ぶのが賢い選択です。
ベンチレーション:操作のしやすさ、大きさ、ゴワつきなどをチェック

ベンチレーションは行動中にオーバヒートしてしまうのを防ぐために設けられた換気口です。ハードシェルジャケットは行動中は常に着用することが前提になっているため、ほとんどのモデルにベンチレーションがついています。
開閉部が大きいほど大きく換気できるので便利ですが、ジッパーの開閉操作がスムーズでなかったり、ベンチレーションの位置や大きさによって着心地にゴワつきが感じられたりする場合もあるので、ここもしっかり試着して自分にフィットしているか確認した方がいいポイントです。
襟部:着た時にアゴと干渉しないかをチェック

防風時には顔を守ってくれる襟部ですが、これもメーカーやモデルによってデザインが違い、着心地に大きく関わってきます。
ハードシェルジャケットを着てみて、ジッパーを上まで閉めた時の襟の位置、ゆとり具合(キツすぎないか)もしっかりと確認しましょう。地味だけど意外と重要なポイントです。着用中にあごに当たる位置にきてしまうとストレスになります。襟が高すぎて着用するとあごに干渉し丸まってしまうようなこともありますから、生地のハリなどチェックしてみてください。
ハードシェルジャケット選びで大切なポイント5:サイズ感・着心地を確かめる

いくら性能と機能が十分に備わっていたとしても、着心地が悪ければ台無しです。用途のところでも解説しましたが、基本的に同じハードシェルジャケットでも、アルパインクライミング向けは身体のラインに密着したスリムなシルエットになっていたり、BCスキー(スノーボード)用なら逆にややゆったりめの作りになっていたりと、それぞれのアクティビティに適したデザインになっています。それ以外にも、各メーカーやトレンドによって細部の作りやフィット感が変わってきますので、流行りのメーカーやデザインだけで選ぶのではなく、購入前にはしっかりと試着してから選ぶのが理想です。
またサイズ感に関しても、メーカーやモデルによって想像と異なることが多々あります。ジャストサイズすぎるのは、重ね着したときに窮屈になったり、身体を動かしたときに突っ張り感があったり腕が出たりするかもしれませんので、試着の際には行動中を想定して手を上げてみたり、伸ばしてみたりといった、できる限り行動を想定したレイヤリングや動きを試して、見落としがないようにしましょう。
まとめ
ハードシェルウェアは堅牢な作りで、過酷なアウトドアで身を守ってくれます。自分に合ったハードシェルウェアを見つけてフィールドへと出かけましょう!
昨今では環境への配慮から、リサイクル素材が使われていたり、これまで撥水加工に使われてきたフッ素化合物を含まないPFCフリーのモデルが一般的になってきています。自然の中で行動するためのウェアが自然に優しい素材や加工により製造されるのは嬉しいことではありますが、これまでのようにノーメンテで長く撥水が維持できるものは少なくなってきています。
お気に入りのハードシェルを見つけたら、定期的にメンテナンスをし、性能を維持させて長く使いましょう!
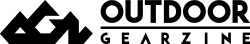
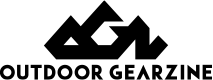






























 【2025秋冬】ダウン?化繊?フリース?快適なレイヤリングのカギは素材選びから。登山向けミッドレイヤー(防寒着)のタイプ別ベスト・モデルと、失敗しない選び方のポイント
【2025秋冬】ダウン?化繊?フリース?快適なレイヤリングのカギは素材選びから。登山向けミッドレイヤー(防寒着)のタイプ別ベスト・モデルと、失敗しない選び方のポイント 【2025秋冬】秋冬アウトドアに欠かせない化繊インサレーション約200モデルから選んだ、用途・こだわり別ベストモデルと失敗しない選び方のポイント
【2025秋冬】秋冬アウトドアに欠かせない化繊インサレーション約200モデルから選んだ、用途・こだわり別ベストモデルと失敗しない選び方のポイント 今年たまらず手に入れた、おすすめハードシェルジャケット10着【2016-2017】
今年たまらず手に入れた、おすすめハードシェルジャケット10着【2016-2017】 【2025秋冬】200着以上を比べて選んだ今シーズンの季節・目的別おすすめベースレイヤーと、自分に合った最適な一着の選び方
【2025秋冬】200着以上を比べて選んだ今シーズンの季節・目的別おすすめベースレイヤーと、自分に合った最適な一着の選び方