
比較レビュー:軽量バックパック大検証 あなたのファストパッキングスタイルに最適なモデルは?
ファストパッキング――。歩きが基本のトレッキングや登山とは違い、普段より軽量な装備で余裕があれば走りもする登山スタイル。より早く・より遠くへ進むというコンセプトの元、最近になって市民権を得てきた新しいジャンルの登山です。人気と共に、近年ではそれに即した新しいコンセプトの道具も多くつくられるようになりました。
ただ一言でファストパッキングといっても、開発するメーカーによって解釈は微妙に異なり、そのメーカーの得意分野によってもさまざまなスタイルの「ファストパッキング」向けアイテムが存在しています。
今回は、そんな多様なスタイルのファストパッキング用アイテムのなかでも軽量タイプのバックパックにフォーカスし、ウルトラライトハイク(ULハイク)の有名メーカー、山岳競技へ注力しているメーカー、アルパイン道具のメーカーなどから選定し、比較しました。
読んでいただければ、今年にバックパックのトレンドから各アイテムの特徴なども分かってもらえるのでは、と思っています。購入したいけど、どこを比較すればいいか分からない、どれが自分に向いているかいまいちピンとこない!という方の手助けにもなれば幸いです。
目次
目次
今回比較した軽量バックパックについて
以下は今回比較したのは軽量バックパック8モデル。基本は、各メーカーがファストパッキング・スピードハイクをして使用でいるバックパックとしてリリースしているものの中から選定してみました。しかしそうした中でも、もちろん各メーカーULハイク、レース仕様など得意分野があります。
今回は新旧各メーカーから販売されているファストパッキング・スピードハイク向け軽量バッグを比較し、そのバッグそのものの評価はもちろんのこと、実際にファストパッキング・スピードハイクに適しているのか、それ以外にも使い道があるのではないかという視点からも、新たな道も探ってみました。
- MONTANE:トレイルブレイザー30
- Gossamer Gear:Camo Kumo36
- PaaGoWorks:RUSH 30
- mont-bell:アルチプラノパック30
- Mountain Hardwear:サミットロケット30
- The North Face:エフピー30
- macpac:フィヨルド28
- Terranvoa:レーサー30プロ
テスト環境
評価項目については、以下の5点を指標を設定し、泊まり想定で8kg/15kgの荷物を入れて山道を歩く・走るなどを繰り返し各項目のテストを行いました。星の数については今回評価した8点全体の相対評価となっています。その中で、どのような用途に向いているかを選別しました。
- 快適性・・・一日中、長い時には何日もずっと背負い続けるバックパック。その間いかにストレスなく快適に背負えるか。
- 重量・・・実際の重量はもちろん、背負った際の重量感も考慮しました。
- 機動性・・・時には走りスピードが早いファストパッキング。しっかりと安定して荷物を支えてくれるのか。
- 機能性・・・ファストパッキングに役立つ機能などが備わっているか。
- 耐久性・・・どうしても重量が軽くなると犠牲になるのが耐久性。軽量でも耐久性をどれだけ確保しているのか。
- 収納性・・・行動中荷物の出し入れを減らしたい中、いかにストレスなく必要なものを収納できるか。
テスト結果&スペック比較表
スマホ向けの軽量表示で表が見づらいという方はこちら
各モデルのインプレッション
ハードな行程から普段使いまで。バランスのよい高性能バックパック
MONTANE トレイルブレイザー30
ここが◎
- 高いフィット性
- 収納性
ここが△
- さらに軽ければ◎
MONTANEのベスト型ファストパッキング用バッグであるトレイルブレイザー30は、まさに何日間もより早くより遠くへ進むための軽量バッグ。特筆すべきはそのフィット感。バック・ショルダー・ウェストと、パッドはそこまで厚くないので、これ大丈夫か?と思ってしまいますが、実際背負ってみると見事に荷物のウェイトが分散されその薄さを感じさせないほど、バランスのとれた快適な背負い心地です。それを実現させているのが、各所細かくフィッティングが調整できるシステムを採用しているためです。まず背面は、ZephyrADをいう背面の調節機構。サイズはユニセックスワンサイズながら、身長に合わせて無段階に調整可能なことから、自分のサイズに合わせて調整することができます。他にもCONVALENTハーネスシステムにより、ショルダーストラップの腰の部分は、2点で支えることにより安定感向上とウェイトの分散を行なっています。ウェストハーネスもポケットとハーネスを分離させ、荷物に関係なくしっかりと腰回りを支えてくれます。
収納もしっかりと確保されています。外部ポケットは非常に充実しており、雨蓋・フロント・サイド×2・ウェスト×2・ショルダー×2の合計8つ。ショルダー・サイド以外はストレッチメッシュ製です。全てのポケットが大きめなので、行動中に必要なものは全て収納可能で、行動中はバッグの上げ下ろしは全く必要ないでしょう。ショルダーのポケットには500mlのフラスコも入れることができます。個人的には、雨蓋のポケットはメッシュでなく防水性のあるポケットだと、もう少し便利かと思いました。外観はポケットが多いせいかごちゃごちゃしているように見えますが、実際は非常にシンプルで、無駄のない作りです。
重量に関しては824gと、そこまで軽量!というわけではなく、取り外せるパーツもないのでこれ以上の軽量化は望めません。しかし、実際に背負ってみた感覚は非常に軽量で軽快。それもこの非常に高いフィット感のなせる技なのでしょう。70Dと210Dの生地を場所に応じて使いわけ、耐久性にもこだわりを見せていることからも、メーカー自身闇雲に重量を落とすよりは、実際の使用感を重視しています。しかしいくらフィット感が高く軽快とはいえ、どちらかというと、全体の行程で走ることが多い人や競技向けのような作りだという印象です。ULハイクや、早く進みたいけどそんなガチじゃない…という人は他の選択肢も検討してみた方が良さそうです。
ハイスピードハイクを支える、体を包み込むようなフィット感
PaaGoWorks RUSH 30
ここが◎
- フィット感・安定感
- きめ細かい収納
ここが△
- 荷物が少ないときの安定性
RUSH30は、日本のメーカであるPaaGoWorksが手がけるRUSHシリーズで、最大容量のファストパッキング用バッグです。これまでに手がけた商品のフィードバックをもとにアップデートされた、高い安定感・フィット感、そして使い勝手の良さを実現したモデルです。
RUSHの特徴であるボリュームのあるショルダーパッドは体を包み込むようにホールドしてくれ、安心感を覚えます。特徴的なのは雨蓋。閉める方向が通常と逆で、雨蓋をとめるバックルがショルダーハーネスについているという、トリッキーな仕様。しかし、このバックルをしめコードを引っ張ると、リュック全体の重心がググッと上の方に引きずられ、ちょうど肩甲骨あたりにかかります。そしてフロントのドローコードでコンプレッションをかければ安定感は非常に高い。実際歩いたり走ったりしてみると、ウェストハーネスがなしでもバッグが揺れずらく、感動を覚えました。他にもショルダーハーネスの厚く広いパッドや、根元を2点で支える細工もその安定感に一役買っているのでしょう。しかし荷物が少ないと、やや安定感に不安があります。やはりもう少ししっかりとしたウェストハーネスがあると、安定感は向上しそうです。
ポケットは、サイド×2、フロント上部×1、ショルダー(大・小)×2の、合計7つ。全てストレッチ性のあるメッシュ仕様でかなり容量が入ります。ショルダーストラップのポケットは大・小一つずつで、下部の大きいポケットには500mlのペットボトルがすっぽりと入り、上部の小さいポケットには、小さいとはいえ6インチのスマホなら収納できるほどの大きさはあります。これだけのポケットがあれば、行動中にメインコンパーメントを漁ることもないでしょう。しかし今回レビューしたバッグの中では唯一、メインコンパーメントにアクセス可能なサイドジッパーを備えています。バッグ内に、完全防水のポケットがあるのも何気に重宝します。
重量に関しては692gと軽量で、背中のメッシュパッド(50g)、バッグ内の背面パッド(35g)は取り外しできるので、最小重量は607gとなりました。メッシュパッドは取り外して洗濯したり、休憩中に乾かしたりと意外によく考えられたギミックです。とても軽量に仕上がっていながら、高い安定性・フィット感をトレードオフしていないという点で、重量にこだわるULハイカーも、高い運動量でガシガシ進み続けるファストパッカーにもオススメの一品です。
ULのスペシャリストが、日本を意識して開発したバックパックの最新版
Gossamer Gear Camo Kumo36

ここが◎
- 背負い心地・快適性
- 高いカスタマイズ性
ここが△
- 重量制限がシビア
Gossamer Gearといえば言わずと知れた、アメリカのULギアメーカーです。今のULが台頭しているのも、このメーカーによるものは大きいでしょう。そんなGossamer Gearが手がけるバックパックでも、このCamo Kumo36は、軽量バッグKumo36をベースに、100D Robic Camo Jacquard fabricにUTS(Ultra Tearing Strength:超引裂強度)コーティングを施した生地を使用して、より耐久性を向上させたモデルです。確かにこの生地のおかげで重量はKumo36 (595g)より100gほど重くなっていますが、耐久性の向上により、より長くよりハードなトレイルに連れて行くことができます。
Kumoの特徴として、かなりULに寄った作りだということです。フレームレスボディー、ベルト類全て細く、バックル類も全て小ぶりで簡易的なものを使用しています。そのため重量は本来のKumo36より100gほど重くはありますが、最低重量で524g。しかし軽いだけでなく、厚めの3Dメッシュパネルを使ったショルダーストラップ、取り外し可能なウェストストラップ(103g)などで長時間のトレッキングも快適です。もちろん背中のパッド(65g)も取り外し可能で好みのアレンジが可能です。シリアスなULハイカーでも十分満足のいく仕様です。
シンプルで機能美に溢れる外観は、右肩にかけた時に手を入れやすい斜めのフロントポケット、口にゴムを使い中身が落ちにくいサイドポケット×2、ショルダーストラップのポケット×2、そして雨蓋の止水ファスナーを使ったポケットと、必要十分な量を外部ポケットに収納できます。特に防水の雨蓋ポ
ケットはありがたい。ポケットは全てやや小さめですが、問題ないでしょう。体にぴったりとフィットるすような高いフィット感はありませんが、背負って歩く分には十分な安定感をもたらせてくれます。ウェストストラップを取り付ければより向上します。走りを多用する使用には不安がありますが、ULハイクでは、文句のない高性能バッグとして良い相棒になってくれるはずです。あと、25ポンド(11.3kg)の重量制限があるので、注意が必要です。
とにかくコスパ重視!防水性もあり安心感抜群!
mont-bell アルチプラノパック30

ここが◎
- コストパフォーマンス
- 防水生地
ここが△
- 外部収納が少ない
国内アウトドアメーカーの雄、mont-bellがリリースしたファストパッキングバッグ、アルチプラノパック30は、ロールアップ式の防水軽量バッグです。本体生地にはmont-bellの軽量・高耐久性の30Dバリスティックナイロンリップストップを使用しています。それに加え、防水性の40Dリップストップナイロン製の内袋「アクアバリアサック」を備えています。雨が降り続いても、本体と内袋を分離させられるので、内袋だけテント内に持ち込むという使い方も可能です。バックパネル・ショルダーハーネスは、他のファストパッキング用バッグと比べるとかなりしっかりとした作り。ショルダーハーネスのパッドはかなり厚く、安定感・快適性は抜群。バックパネルもフレームが内蔵され固めですが、肩甲骨あたりと腰部分には通気性のあるメッシュ生地のクッションが配置されているので、長時間背負っていても通気性・快適性共に高めです。
ポケット類は多くなく、外観は非常にシンプルな作り。ストレッチのきくポケットがサイドに1つづつ、ウェストハーネスに1つづつ、そしてショルダーハーネスにも1つづつの合計6つ。ポケットは防水ではないので注意が必要です。胸のポケットは結構大きめで、600mlのボトルが入るほど。そのため、補給食はもちろんのことデジカメなどのやや大きめのものまで入れられるのでは結構便利です。多少重量があるものを入れても、ショルダーハーネスはしっかりとしているので、そこまで気になりません。オプション(別売)で雨蓋(L.W.トップリッド、3.5L、120g)もあるので、容量を増やしたい、外部にもっと収納が欲しいという要望にも答えてくれます。
シンプルな作りながら、ファストパッキングには便利な細かい部分も考慮されています。本体サイドには荷物の量に合わせてコンプレションをかけられるドローコードや、体とバッグの距離を近づけられるような調整コードなど、必要な機能は備え付けられています。薄く耐久性のある生地を使ってはいますが、ショルダーハーネスやバックパネルがしっかりと安定感・快適性を高める作りなので、重量は実測924gと、今回のバッグの中では重め。内袋(82g)を外すことはできますが、せっかく防水性の高さが無駄になるので、そこの軽量化は考えない方が良さそうです。値段もリーズナブルでこの機能性を誇るアルチプラノパック、コストパフォーマンスの非常に高いファストハイキングバッグです。
スピーディーなハイクを可能にする、超軽量アタックバッグ
Mountain Hardwear サミットロケット30
ここが◎
- 軽量性と必要十分な安定性・快適性のバランス
ここが△
- 外部収納が足りない
サミットロケットは、Mountain Hardwearがアルパインのスピードクライムを得意としていたウーリー・スティックのために開発したアタックパックです。作りは非常にシンプルで、外部にポケットは雨蓋に一つあるのみ。とにかく頂上に突き進むために作られています。ULハイクやファストパッキング用ではありませんが、それに耐えうる軽量性・フィット性を持ち合わせるバッグです。
バックパネルには薄めですが通気性が確保されたクッションが圧着され、その裏にはハードウェーブシートという、波状の硬質プラパネルが取り付けられています。このパネルは取り外して70gの軽量化が可能ですが、バッグ自体はふにゃふにゃになってしまうので、注意が必要です。肩のストラップにも背中と一緒の薄手のクッションが付いているので、ULハイクでは問題ないでしょう。ポケットは雨蓋に一つあるのみですが、このポケット結構大きめなので、行動食やレインウェアなどは入れることはできるでしょう。しかし荷物を出すにはバッグを下ろさないといけないので、やや手間が増えてしまいます。
重量は524gと超軽量で、背中のプラ板・コンプレッションコードを外せば、100g弱の軽量化が可能で、420gほどとスマホ2個分くらいの重量になってしまいます。重量は非常に軽量ながら、ファストパッキング用に作られたバッグと比べると安定性・フィット感は低くなってしまいます。しかしやはり超がつく軽量さ、ある程度のフィット性・安定感は持ち合わせているので、重量にストイックなULハイカーには変化球的なバッグの選択肢になるのではないでしょうか。
背負い心地はNo.1。ビギナー向けバックパック
The North Face エフピー30
ここが◎
- 背面パッドの快適性
ここが△
- 重量
ベスト型のショルダーハーネス、ロールトップ式のファストパッキング用のバックパック。名称のFPは、F(ファスト)Pパッキングの略かと思われます。特徴は何と言ってもバックパネル。全体がアルミフレームで支えられ、テンションが掛かったメッシュが張られているので、背中とバッグの間に隙間ができ直接触れ合わないことから、通気性を確保しています。これはトランポリン構造と呼ばれ、通気性だけでなくフィット感の向上にも寄与しています。フレームがあることから、パッキング重量が重くなると他のバッグではバックパネルに工夫が必要ですが、そのままでも安定感は抜群です。
メインコンパーメンとはロールトップ型で、サイドからなど他にアクセス口ははないので、パッキングには工夫が必要です。ロールトップ型なのと、サイドの紐でコンプレッションをかけられるので、荷物の容量の調整は柔軟に対応でき、荷物が少なくても安定してくれます。外面のポケットはショルダーストラップ×2、ウエストストラップ×2、サイドポケット×2、フロントポケット×1の合計7つと多め。ショルダーストラップのポケットは比較的小さめですが、ストレッチが効くので500mlのペットボトルがなんとか入る大きさ。同じ様にストレッチの効くサイドポケットとフロントポケットは比較的大きめで、行動中の荷物は全部入れられるので、無駄にメインコンパーメントを漁らずに済みそう。
このアルミフレームは取り外すことができる様になっていて、その重量は162g。フレームを外せば本体は762gとより軽量になりはしますが、せっかくのポジティブポイントであるトランポリン構造が全く機能しなってしまうことから、そこまで軽量化を狙うのであれば、他の軽量バッグを選んだ方が良いはず。ファストパッキング用バッグではありますが、生地も太めのナイロン糸を使い耐久性を向上させたり、圧倒的な軽量化へ走らず背負い心地・安定感を狙ったバッグであるため、ファストパッキングを始めたいけど、思いっきり軽量化に傾いたバッグはちょっと不安…と感じている人には良い選択になりそう。アルミフレームを外す余地もありますしね。
高いクッション性で、重量がかさんでも長時間楽々
macpac フィヨルド28
ここが◎
- 耐久性
- 重い荷物での安定性
ここが△
- ショルダー部分のポケットが欲しい
macpacは、Simplicity Beyond Complexity:シンプルであれ!を基本理念とする、ニュージランドで生まれのアウトドアバッグメーカーです。今回のバッグ・フィヨルド28も、その理念に基づいたシンプルかつ機能性の高いバックパックです。ロールトップ式と、サイドのドローコード、その名も「ZigZagサイドコンプレッション」で荷物にコンプレッションを効かせることができるため、容量を自在にコントロールできます。それに加えショルダーとウェストハーネスには、体とバッグの距離を近づけるための調整コードがあるので、早いテンポでのハイクに安定感を与えてくれます。ショルダーパッドは他のバッグに比べると厚めで、長時間の仕様にも心地よい背負い心地が続きます。バックパネルは凹凸があり厚めの波状ウレタンフォームにメッシュを用いているので、フレームがないとはいえ、安定性・通気性・クッション性を確保しています。
メインコンパーメンとはロールトップ式で、ロール部分はやや長め。アクセスは一ヶ所のみなので、パッキングに工夫が必要となります。しかしメッシュポケットがサイド×2、フロント×1にあるので、行動中に必要な荷物はこちらに入れておくことができます。メッシュ仕様なので、中身がうっすらと見えるのも嬉しいところ。ショルダーハーネスにはポケット類はなく、正面のポケットはウェストハーネスのポケットのみ。容量はある程度確保されているので補給や小物を入れるのには問題ありませんが、止まる間も惜しんで給水したい!という人はハイドレーションを使うことになります。ファストパッキング用はやはりショルダーのポケットは欲しいところです。
全体重量は実測値で894gと、今回のフレームレスバッグでは最重量ですが、他と比べ耐久性の高い素材を使用しているので、そこはどちらを優先するか…ということになるでしょう。それでも900gを切っているのは十分軽量といえます。とはいえ、使っていてもう少し軽い方がよかった…なんて思った時は、バックパネルのウレタンフォーム(48g)と、ウェストハーネス(214g)は取り外すことができるので、両方外せば630gほどにまで軽量化できます。ウエストハーネスを外すことで安定感は低下してしまいますが、色々工夫もできそうなので、そこまでスピードを出さず、軽量化を求める人には良いかもしれません。
超ストイックに攻めたい、とにかく重量志向なあなたへ
Terranova レーサー30プロ
ここが◎
- シンプルで軽量
ここが△
- 快適性
超軽量テントで有名なテラノバのレーサー30プロは、30Lの容量ながら500gを切る超軽量性を誇るテラノバらしいバッグです。しかしただ軽いだけではなく、必要な機能はしっかり確保され、実用にも十分耐えうる仕様となっています。やはり特徴はメインコンパーメントへのアクセスです。非常に潔く、上から下までガバーッと完全に開いてしまいます。しかし、これが結構使いやすく、バッグを下に置いてジッパーを開くとボストンバッグのように中身が全部見ルことができるので、荷物がとても取り出しやすい。パッキングの際もそれを生かして適当に詰め込んでも、背中にパッドが入っているのでそれなりに安定します。ショルダーストラップも重量の割にはクッションが入っているので、多少重くなっても肩への負担を減らすことができます。
機能性も高く、ショルダーストラップにはドローコード付きポケット、ウェストハーネスにはジッパー式ポケット×2、ドローコード付きポケット×2、フロントのメッシュポケット×2、そしてフロントポケットやや上部にジッパー式スリーブポケットと、数では9つのポケットがあり、ジッパーは全て止水仕様で、多少の雨であれば気にせず突き進めます。フロントのメッシュポケットは、ゴム製ドローコードがついているので、これを絞ればポケットの中身が落ちにくくなり、全体的に荷物が少ない時にはコンプレッションの役目も果たしてくれます。そしてボトム部分にはマットやポールを留めるストラップもついています。
やはり軽いのは正義です。しかも軽いだけでなく走っても揺れない安定感も持ち合わせています。背中のパッド(36g)を外してさらなる軽量化も可能なので、宿泊を前提とした装備を背負って、とにかく早く・遠くへ進みたいストイックな競技志向の人にはうってつけ。しかし快適に背負い続けられるかと言われると、そうでもないので、ある程度の快適性を求める人は選択肢から早々に外した方が迷いが減るのではないでしょうか。
まとめ
今回は、ファストパッキング向けの軽量バックパックを実際に使用して比較評価してみましたが、やはり選んだモデルはどれも基本的には優れたパフォーマンスを発揮してくれることは間違いありません。
なかでも、ランニング・トレッキング両方で万能に活躍してくれるトレイルブレイザー30、RUSH 30は総合的に高い性能と使い勝手を発揮してくれます。トレイルブレイザー30は背面長の調節機構も持ち合わせ、万人に高いフィッティングで安定感を提供してくれることから、総合的に見て1番のおすすめといえそうです。またRUSH 30の大きめのショルダーストラップも、体を包み込むフィットによる高い安心感も捨てがたく、これらは他のバッグの追随を許さないほどでしょう。
またサミットロケット30は、多くを削ぎ落しながら安定感を損なわず、長い距離も歩けそうです。少しでも重量を削りたい人には良い選択肢になりうるバックパックでしょう。
Camo Kumo36やアルチプラノパックはそこまで走りを意識していない軽量バックパックとして優秀です。
エフピー30やフィヨルド28などは重量こそやや重めですが、背負い心地の快適性は他のモデルに比べるとより普通のバックパックの安定感に近いといえるため、これからULハイクを始めてみよう!という人にとっては適したバックパックといえそうです。
バックパックは場所を取るので、よほど好きでない限り何個も持っているという人は少ないのではないでしょうか。今回の記事を読んで、自分が何をしたくて、自分にはどのようなスタイルが合っていて、何が必要なのか考えるきっかけになり、良いバックパックを見つけるきっかけになれば幸いです。
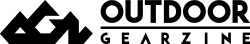
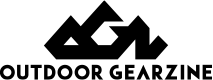


![[ザ・ノース・フェイス] リュック エフピー30 L ティングレー](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/71D1jZCHjxL._SS300_.jpg)

![[マックパック] リュック フィヨルド28 ボタニカルガーデン](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/91SvAdvUWLL._SS300_.jpg)






















 比較レビュー:身軽な山歩きやファストパッキングにピッタリな軽量バックパックを比べてみた
比較レビュー:身軽な山歩きやファストパッキングにピッタリな軽量バックパックを比べてみた これからファストパッキングをはじめる人におすすめの軽量バックパック10選
これからファストパッキングをはじめる人におすすめの軽量バックパック10選 比較レビュー:夏山のトレーニングからレースまで!注目のトレイルランニング用ハイドレーションベスト
比較レビュー:夏山のトレーニングからレースまで!注目のトレイルランニング用ハイドレーションベスト 比較レビュー:登山にランに大活躍の超軽量レインウェアを着比べてみた【2016春夏】
比較レビュー:登山にランに大活躍の超軽量レインウェアを着比べてみた【2016春夏】