
【2025-2026】決してブランドイメージだけで判断するなかれ。登山向けスリーピングバッグ(寝袋)のベスト・モデルと、後悔しない選び方のポイント
満天の星空の下、心地よい寝袋の温もりに身をゆだねながら眠りに落ちる夜──。実際にはテント内で寝ることが多いとはいえ、大自然との繋がりを感じながらの睡眠は間違いなくテント泊登山の醍醐味のひとつです。
そんなテント泊での快適な睡眠に欠かせないのが寝袋(スリーピングバッグ・シュラフ)。一般的なキャンプ用の寝袋と違って登山用の寝袋は軽量・コンパクトに作られ、持ち運びの負担を最小限にしながら最大限の寝心地と暖かさを提供してくれます。
他の多くの山道具と同じように、一言で寝袋といっても各メーカーは用途や目的、そして季節や場所などによって素材・構造・形・重さなどの異なるさまざまなモデルを用意しており、多様なニーズにフィットするように作られています。多岐にわたる要素や多くのバリエーションの中から自分にとって最適なスリーピングバッグを選ぶということは決して簡単なことではありません。万が一合っていないモデルや粗悪なモデルをつかまされてしまえば、寝不足になったり疲れがとれなかったりと、せっかくの旅が台無しです。決して安くはない買い物、1度購入すれば何年も使い続けることになるであろう大切なパートナーですから、ぜひとも慎重に選びたいものです。
ここ日本では某三大メーカーがなぜか強すぎる傾向にありますが(もちろん品質は高くはあるのですが)、実際には海外のモデルも負けず劣らず、日々確実に進化し続けています。そんな海外のブランドから活きのいい新作が登場し、今シーズンも実りの多い一年でした。
そこで今回は登山歴25年以上の自分が2025-26シーズンの全237モデルを調べ、独自にベストモデルを選出し、後半では最適なモデルを賢く選ぶために気をつけるべきポイントにについてまとめてみました。
なおここでは各部門で1点ないし2点しか紹介しておりませんが、その他のおすすめモデルや、それらを含めたすべてのスペック・特徴を網羅した比較一覧表を、メンバーシップ向けに公開しています。Outdoor Gearzineのコンテンツはみなさんのご支援によって支えられています。ご興味のある方はぜひこれを機会にメンバーシップの加入をご検討ください!
すべてのおすすめスリーピングバッグと全237モデルの比較一覧表は有料メンバーシップで

目次
- 【シーン・こだわり別】ベスト・アウトドア向けスリーピングバッグ
- 総合ベスト・スリーピングバッグ:Rab Mythic Ultra / NEMO コーダ™ エンドレス プロミス® / mont-bell ドライシームレスダウンハガー900
- ベスト・軽量スリーピングバッグ:Sea To Summit スパーク
- ベスト・冬用スリーピングバッグ:ISUKA エアプラス630・810 / THE NORTH FACE インフェルノ-18・-29
- ベスト・低価格で良質なスリーピングバッグ:ZANE ARTS KUMO
- ベスト・キルト・ハーフレングス型スリーピングバッグ:Rab Mythic Ultra 120 Modular / ENLIGHTENED EQUIPMENT Revelation / NEMO パルス™ 20/30 エンドレスプロミス®
- ベスト・低価格で良質なキルト・ハーフレングス型スリーピングバッグ:LEISURES Roo Sleeping Bag 300
- ベスト・化繊スリーピングバッグ:OMM MountainRaid
- ベスト・化繊キルト・スリーピングバッグ:STATIC ADRIFT Ti SLEEPING BAG
- 選び方:登山・ハイキング用スリーピングバッグを賢く選ぶ6つのポイント
- まとめ
【シーン・こだわり別】ベスト・アウトドア向けスリーピングバッグ
総合ベスト・スリーピングバッグ:Rab Mythic Ultra / NEMO コーダ™ エンドレス プロミス® / mont-bell ドライシームレスダウンハガー900
優れたスリーピングバッグに求められる「重量当たりの保温性」の高さはもちろん、快適な寝心地や使いやすさ、そして収納時のコンパクトさといった様々な要素をバランスよく高いレベルで兼ね備えたモデルは、幅広い季節やアクティビティに柔軟に対応しやすく、また初心者からベテランまでも満足いくクセのない使い勝手の良さも相まって、多くの人にとってちょうどいい選択肢になります。そんな誰にでもおすすめできる総合的な優秀さを備えた今シーズンの総合ベストモデルは、非常に悩ましかったのですが「Rab Mythic Ultra / NEMO コーダ™ エンドレス プロミス® / mont-bell ドライシームレスダウンハガー900」の3シリーズを同時選出。
すべてのモデルはそれぞれ細かな個性の違いはあれど、全体的なバランスのよい質の高さには自信をもって太鼓判を押せるモデルばかり。ほとんどのシリーズが春夏・夏・秋冬・冬向けと異なるボリュームのラインナップをそろえていますので、目的や好みに合わせて好きなレンジを選んでみてください。
Rab Mythic Ultraのお気に入りポイント
- 裏地の繊維をチタンでコーティングして生地の通気性を損なうことなく放射熱をバッグ内に反射する構造(TILTライニング)によって同重量でもより高い保温性能(=軽量化)を実現
- 900FPのR.D.S.認定ヨーロッパ産グースダウンに撥水加工を施し、湿気にも強い
ドライシームレスダウンハガー900シリーズのお気に入りポイント
- 軽量かつ高断熱の高品質ダウン
- 羽毛を繊維にからませる独自の手法によってバッフルがなくても偏りなく羽毛を配置できる(=軽量化)
- 表生地に防水透湿生地を採用し濡れにはめっぽう強い表生地
- しっかりフィットしながら動きも妨げない快適性
NEMO コーダ™ エンドレス プロミス®のお気に入りポイント
- 800フィルパワー、撥水加工の十分な高品質RDS認証ダウンを採用
- 適材適所にドラフトチューブが配置され快適な温もりを提供
- 胸部分のマルチステージサーモギルやフットボックスに設けられた放熱ジッパーによってシュラフ内部の温度を調整し、暑すぎ・寒すぎを防ぐ
- 手に取りやすい価格
ベスト・軽量スリーピングバッグ:Sea To Summit スパーク
基本的には全体的なバランスの良さを保ちつつ、若干軽量コンパクトさにフォーカスしたモデル。もちろんダウンの品質の高さ(断熱性)も、快適さも十分及第点、マミー型シュラフとして基本的なシェイプでありながら、隙あらば極力無駄を省いて軽量化が図られているという点でファスト&ライトな登山・ハイキングにピッタリです。個人的にもこの部門が最もしっくりハマるこのカテゴリでの一押しは昨シーズンアップデートした「Sea To Summit スパークシリーズ」がまだ強い。やはりこの軽量コンパクトさと優れた保温性の両立レベルの高さは相当です。
Sea To Summit スパークシリーズのお気に入りポイント
- 高い復元力を備えながら撥水加工の施された850+FPウルトラドライプレミアムグースダウン
- 氷点下に耐える温度域ながら総重量約500グラムという驚異的な軽量・コンパクトさ
ベスト・冬用スリーピングバッグ:ISUKA エアプラス630・810 / THE NORTH FACE インフェルノ-18・-29
上記2部門で紹介したシリーズの冬向けモデルも十分優秀ですが、そこには入っていないけど冬山向けだけを考えたら飛び切り魅力的なモデルというのがこちらの2モデル。
ダウンの一般的な品質指標である「FP(フィルパワー)」は実際のところ計測方法などが曖昧だったりするらしく、その意味ではあくまでも参考程度の数値と考えるべきものだったりします。
その点、ISUKAのダウンの品質実際に使ってみるとそのスペックだけでは分からない品質の高さを備えており、その保温力と寝心地の良さは確か。そのISUKAの中でも最高品質のダウンを使い、熱損失を最小限にする構造を追求した「エアプラスシリーズ」は冬山登山の強い味方です。
またノースフェイスの「インフェルノシリーズ」は極地での使用を想定したエクスペディション用モデルで、撥水加工を施した高品質なPROダウンに、断熱と熱反射効果を高めるXReflex加工を施したシェル生地によって高い断熱性を実現したハイテクモデルです。
ISUKA エアプラスシリーズのお気に入りポイント
- 軽量で抜群の復元力を備えた高品質なグースダウン
- 細部まで丁寧に作り込まれた熱損失を防ぐ工夫
THE NORTH FACE インフェルノ-18のお気に入りポイント
- 高品質かつ撥水加工のダウンに、軽量ながら保温性を高める巧みなバッフル構造、断熱と熱反射効果を高めるXReflex加工によって高い断熱性能を実現
- マットレスとのフィットを考えた作り、コンプレッションスタッフサック等実用性にも抜け目がない
ベスト・低価格で良質なスリーピングバッグ:ZANE ARTS KUMO
今シーズン大きな話題と共に山岳向けシュラフ分野に参入したゼインアーツ。その第一弾はどんなものかと思ったら、まさかの超良コスパモデルでした。「ZANE ARTS KUMOシリーズ」は850FPという非常に高いレベルのグースダウンを使用し、低温度域に合わせたボックス構造、ゆとりのある設計、使いやすいジッパー、隙間にはダウンチューブといった高い保温効率を提供しつつ、驚きの低価格に抑えました。その他のモデルでは「Mountain Hardwear ビショップパス」もなかなかの掘り出し物。
ZANE ARTS KUMOシリーズのお気に入りポイント
- 軽量で抜群の復元力を備えた高品質なグースダウン
- ゆとりのあるシェイプ
ベスト・キルト・ハーフレングス型スリーピングバッグ:Rab Mythic Ultra 120 Modular / ENLIGHTENED EQUIPMENT Revelation / NEMO パルス™ 20/30 エンドレスプロミス®
ある程度旅慣れてきて、自分にとって余計なものが何か分かってきた頃にこれ以上なくちょうどいい選択肢となる可能性を秘めているのが「キルト型」や「ハーフサイズ・フードレス」のスリーピングバッグ。基本的には背面や頭部などの、他で代替可能な部分を省略したデザインにすることで、よりいっそうの軽量化を図ったモデルです。
また単に軽くて暖かいシュラフとしてだけでなく、ブランケットになったり、冬の追加シュラフとしても使い勝手もよいため、近年ではウルトラライトやファストパッキングはもちろん、バイクパッキングやソロキャンピングなど幅広い層にまで普及してきています。
長年ウォッチしている限りでは、ここ数年、この分野での新製品、新規参入が最も多く、現在の寝袋市場で最もホットなジャンルといえるでしょう。それだけに、ユニークなアイデアや先進的な技術に基づいたキラリと輝く新製品が多く、ひとつに絞り切るのが非常に難しかったです。
その中で品質の高さと、個性、そして欠点の無さなどを総合して、3つのモデルを選出しました。中でも今シーズンの新作NEMO「パルス™ 20/30 エンドレスプロミス®」はこれまでの人気モデルの良いところを踏まえつつ、さらに1000FPという最高品質の撥水ダウンにゴールドを混入し、最高レベルの重量比保温性を実現したダウンを採用するなど非常に競争力の高いモデル。価格も挑戦的ですが、これだけのプレミアムな機能が詰め込まれていればそれだけの価値はあるでしょう。その他の2モデル「Rab Mythic Ultra 120 Modular」と「ENLIGHTENED EQUIPMENT Revelation」に関してはOutdoor Gearzineでもレビューしましたが、その実力の高さは健在です。
NEMO パルス™ 20/30 エンドレスプロミス® のお気に入りポイント
- このカテゴリーで最高レベルの重量比保温性を実現した1,000FPのExpeDRY ゴールドインフューズドダウン
- コールドスポットの発生を防ぎ、ダウンを均等に分散させ、軽量化にも貢献する独自のバッフル構造
- 通常の寝袋では考えられない500グラムで下限-5℃という温度域を実現
Rab Mythic Ultra 120 Modularのお気に入りポイント
- 裏地の繊維をチタンでコーティングして生地の通気性を損なうことなく放射熱をバッグ内に反射する構造(TILTライニング)によって同じダウン量でもさらなる保温性向上(=軽量化)を実現
- 900FPのR.D.S.認定ヨーロッパ産グースダウンに撥水加工を施し、湿気にも強い
- 背面を省略してマットレスを合わせることで、330グラムという軽さで0℃という限界温度を実現(Rab独自基準)
ENLIGHTENED EQUIPMENT Revelationのお気に入りポイント
- 850以上の軽量かつ高い断熱力の高品質ダウン
- 耐久性、通気性、軽量性、ダウン抜けの無さが素晴らしいシェル生地
- ダウン品質からダウン量、サイズ、色等、自分の好みのスペックが選べるカスタマイズ性の高さ ※ただし本国英語サイトで直接購入する必要あり
- 足元のジッパーを全開すれば1枚のキルトにもなる汎用性の高さ
ベスト・低価格で良質なキルト・ハーフレングス型スリーピングバッグ:LEISURES Roo Sleeping Bag 300
前述したキルト・ハーフレングスはさまざまなブランドが参入してきてくれたおかげで多彩なモデルが登場、中でもコストパフォーマンスに優れたモデルもいくつか出てきています。この「LEISURES Roo Sleeping Bag 300」は安曇野のセレクトショップ「LEISURES」のオリジナル製品。日本人に最適化されたサイズ感、フードとファスナーを省いて、極限まで軽量化、コールドスポットを少なくしたボックス構造など、軽量・コンパクト化とダウンの保温効率を両立させることにこだわってます。このこだわりに加えて、かなり頑張った価格設定も見逃せません!
LEISURES Roo Sleeping Bag 300のお気に入りポイント
- フードとファスナーをはじめ無駄な部分を極限まで省いた軽量コンパクト設計
- 軽いながらも熱損失を抑えた保温効率の高さ
- 手の届きやすい価格設定
ベスト・化繊スリーピングバッグ:OMM MountainRaid
どうしても悪天候や濡れを避けられない沢登りや長期縦走などには、いくら防水対策が施されていたとしてもダウンより化繊の方が安心して携行できます。
「重い・かさばる」といった点がネックだった化繊中綿も最近では目覚ましい技術革新によって昔に比べて非常に軽量・コンパクトになり、持ち前の低価格・手入れの簡単さもあって、最先端の化繊シュラフは決して悪くない選択肢といえます。そんな化繊ベストシュラフの筆頭は「OMM MountainRaid」を挙げたいと思います。
OMM Mountain Raidに採用された中綿「Primaloft Gold with Cross Core Technology」は未来の断熱素材、エアロゲルを混入し、ダウンに引けを取らない対重量比保温力を誇ります。おまけに濡れても保温力を保ち、湿気の多い季節でも、水辺でのアクティビティでも安心です。
OMM MountainRaidシリーズのお気に入りポイント
- 通気・速乾性に優れ濡れにも強く、そしてダウンに匹敵する高い断熱性を備えたた「Primaloft Gold with Cross Core Technology」中綿を採用
- 化繊なのに軽量・コンパクト
ベスト・化繊キルト・スリーピングバッグ:STATIC ADRIFT Ti SLEEPING BAG
化繊のメリットを備えながら、弱点であるかさばり・重さなどを克服した「化繊かつキルト」というスタイルは、気温が高く湿度の多い春夏シーズンの登山や沢登などのバリエーションにベストフィットする可能性を秘めています。
実際今シーズンの沢登りや夏のテント泊登山で最もお世話になったのがこのインナーシーツ並みに薄っぺらいにもかかわらずめちゃくちゃ快適なハーフレングスシュラフ「STATIC ADRIFT Ti SLEEPING BAG」でした。
ここ数年大人気、さまざまなアクティブインサレーションに採用され、その軽さと暖かさは実証済みの「Octa®CPCP®」を中綿として採用し、さらに体温の熱を反射して高い保温効果を得られる”チタンスパッタリング”超薄膜コーティング加工を施したことで軽いのに夏に十分な暖かさをくれました。
基本的にはこの部門、夏向けでちょうどよいモデルが多いのですが、探そうと思えば3シーズン向けにも良いモデルがあります。例えば「LITEWAY SLEEPER QUILT APEX 10D」は中綿にここ最近の人気中綿「Climashield® APEX」を採用し、氷点下にも対応できています。
STATIC ADRIFT Ti SLEEPING BAGのお気に入りポイント
- 軽量コンパクトで心地良い肌触り
- 軽さと暖かさを備えたOcta®CPCP®とチタンスパッタリングによる軽量ながら高い熱効率
- 洗濯機で洗える手軽さ
上記のほかにピックアップしたすべてのおすすめスリーピングバッグと全237モデルの比較一覧表は有料メンバーシップで
選び方:登山・ハイキング用スリーピングバッグを賢く選ぶ6つのポイント
ポイント1:対応する温度域を選ぶ ~暑すぎ・寒すぎに注意~
最適な寝袋を選ぶ際に何をおいても大切なのは、正しい「対応温度域」を選ぶこと。対応温度域とはその寝袋で寝る場合、どの程度の気温でならば快適に使用できるかという目安であり、そのシュラフの保温性能を表しているといえます。
昔からスリーピングバッグは気温との関係で大きく以下の3つ程度の分類がなされてきました。
- 夏(1シーズン)・・・真夏の低山や初夏~初秋平地で使用することを想定した寝袋(だいたい5℃以上が目安)。
- 春~秋(3シーズン)・・・春秋の低山や夏の3,000m級の高山に対応したスリーピングバッグ(-8~5℃前後が目安)。
- 冬(4シーズン)・・・冬山や残雪期の高山に対応した寝袋(-8℃以下程度が目安)。

一般的な登山で使用するスリーピングバッグは、基本的には上の分類のような3種類があれば十分ということを示していますが、はじめからすべて揃える必要はなく、このうちまず最低限揃えておきたいのは3シーズン用です。真夏の低山では少々暑すぎますが、それでも使用できないことはないことから、最もカバーする期間が長いことがその理由。その後は活用頻度や予算に応じて夏・冬用を追加していくというのが無駄や失敗の少ない方法です。人によって冬用は3シーズン用+夏用を二重にして使用するなどの猛者もいます。要はここから先はそれぞれのやり方で工夫の仕方も色々あるということです。
近年では同じ3シーズン用のなかでもブランドやモデル次第で温かさはさまざまで、最適な寝袋選びにはさらに細かいチェックが必要です。そのためにあるのが各モデルに必ず提示されている対応温度域表示。かつては各メーカーがバラバラの基準で提示していましたが、近年では国際基準が浸透しつつあります。それがこれから説明するヨーロピアン・ノームです。
断熱性を判断するための便利な指標「ヨーロピアン・ノーム(EN)13537」を活用しよう
最近のスリーピングバッグの多くはヨーロピアン・ノーム(EN)13537と呼ばれる基準に基づく参考適応温度域が示されています。EN13537 は2000年代にEU諸国内で使用されはじめましたが、現時点では最も信頼のおける指標として世界各地に広まりました(それでも決して安くはないテスト費用やその信憑性への疑念からまだこの基準の採用に踏み切っていないメーカーも存在しているのが現状)。この基準では次の3つの指標がセットになって表示されます。
- T-Comfort(快適)は一般的な女性が寒さを感じることなく眠ることができる温度域。
- T-Limit(下限)は一般的な男性が身体を丸めて8時間寝られる温度域。
- T-Extreme(極限)は一般的な女性が膝を抱えるくらい丸くなって6時間耐えられるとされる温度域。場合によっては低体温症になる恐れがあり非常に危険。
【要注意】EN13537 スペックは読み方に注意(数字をそのまま100%信用してはいけない)
そうと分かれば、自分がこれから行くであろう場所の大まかな気温を天気予報などで確認し、それが EN の示す温度域内に収まるようなモデルを選べばよい、ということになりそうです。しかし実際にいろいろなモデルを購入し試してみると、事態はそう簡単ではないということが分かります。端的にいうと、試してみたほぼすべてのモデルが EN の表示ほどに温かいとは感じられないのです。
その大きな原因はテスト方法にあります。EN13537 は実験室という作られた環境で、上下長袖のアンダーウェアと靴下を着用した特定の体型(男性:25歳・173cm・73kg、女性:25歳・160cm・60kg)で測定した結果にすぎません。そこには使用者の国籍・体型・体質・その日のコンディション・着ている服・敷いているマット・中綿の圧縮率といったさまざまな変動要因が考慮されていません。やや乱暴に例えるなら自動車でいうところの「カタログ燃費」みたいなもので、実際にその燃費で走れるとは限らず、あくまでも比較のための指標程度というわけです。
つまりこれらの数値は残念ながら誰もが鵜呑みにできるような数値ではないということではありますが、そうだとしても、統一された計測方法で算出された数値であるという意味では、かつてのようなメーカー毎バラバラの基準よりはマシと考えるべきです。少なくとも同条件での保温力を比較することは可能なわけなので、それを上手く活用するのが現時点での賢い選び方となります。
では実際にどうやって判断するか?
表示された温度域に惑わされないためにどうするか?それは現時点でも、そしておそらくこれからも「確証がない限り常に表示よりも余裕をもった温かさを選ぶ」のが正しいやり方でしょう。
個人差・環境によってもある程度の誤差は生じると考えておく方がよく、使い慣れたブランドや熟練者以外であれば、EN表記(女性の場合は「快適」男性は「下限」)から5~10℃は余裕をもった温度で考えておくのが間違いないと思います。具体的には温かめのモデルを選ぶか、あるいは寒いこと前提で防寒着を多めに持っていくかなどです。それでも万に一つは目論見と違ってしまうこともあると思いますが、その時には重すぎる・暑すぎるという失敗はあれど、低体温症という深刻なリスクは避けられているはず。その教訓を次の選択に活かすことができると考えれば前向きになれます。
なお、メーカーによってはまだ EN による温度域表示ではない場合も考えられますが、その時も基本は同じ。確証がない限り余裕をもった温かさを選ぶのがよいでしょう。
ポイント2:中綿素材 ~ダウンにするか、化繊にするか。そこからも無数に広がる選択肢~
対応温度域で候補を絞り込んだら、次は中綿の種類を検討します。スリーピングバッグの保温力は、中綿が膨らむことによってできる動かない空気の層(=デッドエア)が体温によって温められ、さらに外気を遮断する断熱層となり身体全体を包み込んでくれることによって生まれます。つまり保温力はどれだけデッドエアを蓄えることができるかということにかかっています。ちなみにデッドエアを蓄える空間の膨張具合をロフト(嵩高さ)といい、中綿はできる限りロフトを確保するために超重要な役割を果たすわけです。
中綿に使われる素材には天然のダウンと化学繊維がありますが、現状で重量あたりの保温力が最も高いのはダウンです。軽くてコンパクトで温かい、ダウンのスリーピングバッグを選んでおけば通常の登山ではほぼ間違いはないといえます。ただ、弱点が無いわけではありません。以下にメリット・デメリットの比較表をまとめました。
| 素材 | ダウン | 化繊 | ハイブリッド |
|---|---|---|---|
| メリット |
|
|
|
| デメリット |
|
|
|
| 適した状況や使い方 |
|
|
|
ダウンは高性能ですが、価格が高めで、濡れに弱い。このため軽さ・大きさよりも価格を重視する人や、沢登りなどザックが濡れる可能性が高いアクティビティが多い人にとってはダウンよりも化繊の方が適している可能性があります。ただ幸いなことに最近の化繊中綿の進歩は目覚ましく、今や化繊だから重いとか、快適じゃないとか言ってもいられない状況が眼の前に来ていることは確か。試しに一度お店で実物を見比べてみることをぜひおすすめします。
一方でダウンの方も日々進化を続けています。強力な撥水加工処理を施して弱点である濡れに対する弱さをある程度克服した「撥水ダウン」が多く見られるようになりました。ただ撥水ダウンも濡れに対してはまだまだ限界がありますので、雨や湿気の多い日本では何らかの浸水対策は必須と考えた方がいいでしょう。
品質の高いダウンを選ぶことでより軽くて暖かく(種類・産地・FP・比率について)

ダウンの品質については、TVやラジオでよく見かける通販番組の羽毛布団ではないですが、実際に驚くほどさまざまな要素が品質に影響している世界です。ここではそれらひとつひとつを事細かに紹介することはせず、その代わり良質なダウン・スリーピングバッグを選ぶために知っておくとよいポイントを絞って説明します。
ダウンの種類・産地
より大きなロフトで嵩高性に優れ、高い保温力を発揮し、臭いも少ないなど、最も高品質であることが多いといわれているのがヨーロッパ産のグース(がちょう)から採れたダウンです。一方その他の地域で育てられた水鳥や、グースではなくダック(あひる)から採取されたダウンは(すべてではないものの)中~低級であることが多いといわれています。最高級のグースダウンとなると飼育日数も大きく影響し、丁寧に飼育された21週間後のグースから最高級のダウンが採れるともいわれています。
ダウンのFP(フィルパワー)・比率
 FPとはダウンにおけるロフトの復元力を表す指標で、FPが高いということはそれだけ個々の羽毛(ダウンボール)が大きく嵩高性に優れている、すなわち高い保温性を発揮するといえ、同じ温かさなら高いFPの方が、軽くてコンパクトな寝袋が作れるということになります。上述した水鳥の種類との関係でいうと、ダックからは高くても750~800FP程度までのダウンしか採取できないのに対し、より身体の大きなグースからは900FPか、それ以上の高品質ダウンが採取できると言われています。
FPとはダウンにおけるロフトの復元力を表す指標で、FPが高いということはそれだけ個々の羽毛(ダウンボール)が大きく嵩高性に優れている、すなわち高い保温性を発揮するといえ、同じ温かさなら高いFPの方が、軽くてコンパクトな寝袋が作れるということになります。上述した水鳥の種類との関係でいうと、ダックからは高くても750~800FP程度までのダウンしか採取できないのに対し、より身体の大きなグースからは900FPか、それ以上の高品質ダウンが採取できると言われています。
一般に650以上なら高品質ですが、値が高くなればなるほど価格は跳ね上がっていくため、ダウンを選ぶ際には価格をとるか、保温性・携帯性をとるかという無情な二者択一を乗り越えていく必要があります。
またダウンと一言でいっても、実際にはロフトを稼ぐために若干のフェザー(羽根)を混ぜてあるもので、その割合が90/10などと表示されています(90%ダウン、10%フェザー)。フェザーは保温性を高めてくれる素材ではありませんので、当然ダウンの比率が高い方が保温力が高く、肌触りも柔らかく、品質が高いと考えて良いでしょう。
アニマル・ウェルフェア(Animal Welfare)とダウン
様々な面からより環境へのインパクトを抑えた製品開発へと見直される流れのなかで、ダウンもその製造過程で大きな反省を迫られるようになりました。水鳥からダウンを採取するという行為は実際には水鳥の皮膚に生えている羽をむしり取ることにほかならず、ありていに言えば動物への虐待行為そのものです。効率が最重視されていたかつては、水鳥を早く成長させるために強制的に餌を多く与え(強制給餌)、さらに生後12週目あたりからから大人へと成長するまで、生きているうちに何回も機械によって無理やりむしり取られていました。
現在では家畜にとってストレスや苦痛の少ない飼育環境を目指す「アニマル・ウェルフェア(Animal Welfare)」という考え方が広まっていった結果、一部の寝袋メーカーからこうした非人道的な飼育・採取方法を見直す動きが続々と現れており、特に欧米のマーケットで流通するダウン製品ではほぼすべてこうした考えに即した基準を採用するようになっています。
そこで消費者である私たちが今後ぜひ気にするべき点は具体的に大きくいうと、
- 狭いケージで多く餌を与え続ける「強制給餌」をさせていないこと
- 生きたままの水鳥から羽毛をむしり取る「ライブ・プラッキング」をしていないこと
の2点が守られている羽毛業者から仕入れたダウン中綿を使用しているかどうかです。
 ただこれが守られているかどうかを消費者が逐一チェックするのは手間がかかるだけでなく、メーカーごとに独自の基準を作られては混乱を招きかねません。そこでメーカー側は製造過程全体を監査し、分かりやすいお墨付きを与えるグローバルな第三者機関を策定することで対応しました。その認証が「RDS(レスポンシブル・ダウン・スタンダード)」であり、シュラフだけでなくジャケットなども含め海外メーカーのダウン製品などにはタグがついていることがあります。
ただこれが守られているかどうかを消費者が逐一チェックするのは手間がかかるだけでなく、メーカーごとに独自の基準を作られては混乱を招きかねません。そこでメーカー側は製造過程全体を監査し、分かりやすいお墨付きを与えるグローバルな第三者機関を策定することで対応しました。その認証が「RDS(レスポンシブル・ダウン・スタンダード)」であり、シュラフだけでなくジャケットなども含め海外メーカーのダウン製品などにはタグがついていることがあります。
ポイント3:濡れに対する強さ ~日本では何らかの濡れ対策は必須~
テントでの快適な睡眠のために寝袋は最も重要な道具であることは間違いありませんが、その寝袋は保温性を失ってしまうという事態は何よりも避けなければなりません。つまりシュラフの濡れを防ぐための対策はどんなテント泊山行でも備えなければならないのです。
先程ダウンは濡れると断熱性を発揮できないという弱点があるということを言いました。このため従来ならば濡れが心配なときにはダウンシュラフに防水透湿生地のシュラフカバーをかぶせたり、あるいは仮に濡れたとしても保温力を失いにくい化繊綿の寝袋を選択するなどしなければなりませんでした。もちろんこれらは今でも有効かつ確実なシュラフの濡れ対策ですが、ただこれではダウンのせっかくの長所である「軽さ」が活かせず、実に悩ましい状況が続いていました。そんな状況が最近徐々に変わりつつあります。
ダウンの濡れ対策その1:防水透湿性の高い表地のシュラフ

防水透湿性の素材を使用した寝袋ならば、湿気はもちろん、水滴や水没に対してもほぼ不安はありません。
登山向けスリーピングバッグの表面生地は、まず前提としていかに薄手・軽量性を保ちながら丈夫な生地であるかが品質の良し悪しを決めます。さらにそこから糸と糸との隙間をつぶしてダウンの抜けを防ぐ「ダウンプルーフ加工」がなされていたり、水を弾きやすい「DWR(耐久撥水)加工」を施してあるかどうかなどが見どころ。ただこれだけでは、濡れ対策は十分とはいえません。
濡れに対して十分な対策が施された寝袋とは、例えば表面生地に防水透湿素材を採用していたり、さらに防水透湿素材に加えて縫い目にまでシームテープ処理を施すなどして浸水を完全にシャットアウトしているようなモデルなどのことを言います。これらならば、濡れを防ぐためのシュラフカバーはまず不要で、ダウンの軽さ・快適さを安心して堪能することができるでしょう。
ダウンの濡れ対策その2:ダウンに撥水加工を施した「撥水ダウン」採用のシュラフ
次に先ほども触れましたが、近年目覚ましい革新を遂げつつあるのがダウンが本来持つ撥水能力をさらに高める加工処理を施した「撥水ダウン」です。上の動画で紹介されているNikwax Hydrophobic Downを筆頭に、ダウン中綿自体に高い撥水加工を施すことで濡れても復元力を失いにくいダウンが次々と開発されてきています。動画を見る限りでは、ダウンが水浸しになるような酷い状況にでもならない限りある程度ロフトを保ってくれそうではあり、そこまでシビアな状況でなければ今のところ実用性は高いといえます。
ただそうはいっても、まだこれらの撥水加工ダウンは高品質なピュア・ダウンに比べるとどうしても加工を施すことによる復元力(保温性)の低下、そして製品寿命の低下は避けられません。自分はこれまでレインウェア等でもDWR加工が洗濯などによって徐々に低下してしまう現実を経験してきており、撥水加工ダウンとて何度も使えば撥水性はほぼ間違いなく低下してしまうはずです。その意味で撥水加工ダウンシュラフが長期的な視点で良い製品でかるかどうかは未だに懐疑的。かなり実用性は上がってきているのは確かですが、まだ手放しでこちらを選択すべきとはいえず、注意深く見ていく必要があると思っています。
ポイント4:形状・サイズ・構造 ~マミー型を基本に、慣れてきたら自分なりにムダを省いていく~
基本は「マミー型」。特定の用途に便利な新シェイプにも注目
オートキャンプや車中泊などまで広く考えると、普通の布団のような「封筒型(レクタングル型)」の寝袋もありますが、こと登山向けに限って言えば、寝袋の一般的な形はほぼ間違いなくマミー型と呼ばれる形状が基本です。マミー型は、顔以外をスッポリと覆いながら身体と中綿との間の余分な隙間を極力省いて保温性を最大化しながら、重量をできる限り削減することを意図したシェイプです。

さまざまな3シーズン用スリーピングバッグの形状(左から): マミー型、フード無マミー型、変形マミー型、ハーフキルト型、キルト型、ウェアラブル型、2人用マミー型
はじめて寝袋を購入するといったビギナーの皆さんはこのマミー型がが安全かつ機能的なのでおすすめです。ただ最近はアクティビティやニーズの多様化によって、伝統的なマミー型から派生したさまざまな形状が生まれていることも見逃せません。
これらのモデルは伝統的なマミー型の効率性をさらに推し進め、より無駄を省き、細かなニーズに特化していることが特徴です。
例えば、はじめからマットレスとの併用を前提とすることで裏面をバッサリとカットしたような「キルト型(上写真左から4、5番目)」は、軽量化だけでなく柔軟な寝姿勢(ただし最も密閉した状態になると身体の動きは制限されます)、温度調節性を可能とし、比較的温暖な時期にウルトラライトやファストパッキングをする場合、非常にマッチした形状といえます。
その他、携行している防寒ジャケットを着て寝ることを前提とした「ハーフレングス型(上写真左から2番目)」は肩や胸から上、あるいは上半身全体を省くことで軽量化を実現しています。これらはインナーシュラフとして冬山で他のシュラフと合わせて使い、保温性を追加するのにも都合が良かったりするので、自分の持っている装備全体としてムダを省くこともできるかもしれません。
サイズ
最も保温効果を高めようとするならば、スリーピングバッグと身体との間に余分な空間はない方がよいのですが、あまりにピッタリし過ぎてしまうと窮屈で寝づらい。最高なのは自分の身体のラインにピッタリフィットし、温かさと動きやすさのバランスがちょうどよいサイズのバッグをオーダーメードできることですが、もちろんそんな夢のようなサービスはまだ存在していないわけで、さしあたって今選べるのは多くのメーカーが採り入れているレギュラー・ロング・ショートといった身長・体型別のバリエーションサイズの中から自分にフィットするサイズを選ぶということでしょう(特に女性向けモデルは身長以外にも女性に対応したつくりになっているため強くおすすめします)。
なお、デッドスペースを作らないようにするための解決方法のひとつとして、生地が伸縮するモデルがあります。例えばモンベルのスパイラルストレッチシステムやドイターのインサイドサーモストレッチ・コンフォートシステムなどが有名ですが、試してみると一目瞭然、中綿が身体に密着するので入った瞬間から温かさを感じられ、体感的な保温力は間違いなく数段上で、なおかつ動きも妨げにくく、シュラフを着たままあぐらをかけたりと便利です。
構造
いくら低温に対応した高品質で大量の中綿を使用してたとしても、それだけではまだ安定した保温性を確保できるとは限りません。万が一生地内に封入された中綿が中で移動して偏りが生じてしまったとしたら、中綿の乏しくなった部分ではデッドエアが作れなくなり(コールドスポット)、全体として保温性は著しく低下してしまいます。

光に透かしてコールドスポットを確認しているところ
それを防ぐためにスリーピングバッグは中綿の封入の仕方を工夫し続けてきました。ここではスリーピングバッグの主な中綿構造を紹介しますので、候補のモデルが目的に適った構造を備えているかチェックするとよいでしょう。
ポイント5:その他の要素・パーツ ~実際に利用する際の使いやすさを考えて~
最後にここまでの説明では収まりきらなかった細かいチェックポイントを挙げていきたいと思います。
収納性
スリーピングバッグはダウンよりも化繊が、夏よりも冬と、中綿の質・量によってはかなりのボリュームになり、できる限り軽くてコンパクトである方がいいのは間違いありません。ただ一つ注意としては、そのカタログにあるスペック上の収納サイズは「付属のスタッフサックに入った時のサイズ」でしかないということです。
下の写真のように、購入したままの状態では大きめでも、別売りのコンプレッションスタッフサックを用いることで、さらに圧縮できるモデルもあります。またメーカーによっては標準付属のスタッフバッグ自体がコンプレッション機能を備えている場合もありますので、購入の際には確認しておくとよいです。

フードの作り
首から頭部にかけての部位は多くの熱が発散されているといわれ、保温性の確保にとっては意外と重要。夏用やウルトラ・ライト系ではそれほど重要ではないためカットしているモデルもあります。3シーズン以上のモデルでは頭部を覆うフードが自然にフィットするように作られているか、顔出し口のドローコードは締めやすく邪魔にならず圧迫感がないかなどを確認するとよいでしょう。またより低温での利用を意識したモデルでは肩周りにかけてなどに中綿の入ったチューブを補って冷気の侵入を防いでいるモデルもあり、それらは少ない重量でより快適さを提供してくれます。

フードのつくりがより立体的で、なおかつ対応温度域に合わせてフードや首周りにチューブ状の中綿を当てるなどしているモデルはより快適性が高い。
ジッパー
スリーピングバッグにおけるジッパーの役割は大きく2つ。ひとつは寝袋への出入りがしやすくなること、もうひとつは開閉により通気性をコントロールし温度調節すること。なるべく大きく開いた方が使い勝手は向上します。ただし、少しでも軽くしたいという立場から考えると部品類は無いに越したことはありません。このため軽量化を重視したモデルでは全長の1/2~1/3程度の長さまでしか設けないか、あるいはまったく無いモデルも存在していますので、好みに応じて選ぶとよいでしょう。

短いジッパー(点線部分)は軽量化には大きく貢献するが、出入りしにくい、温度調節しにくいなどの不便さも受け入れなければならない。
その他より低温での使用を意識して、ジッパーの内側ライン上に中綿の詰まった「ドラフトチューブ」を配置し(下写真)、ジッパー部分からの冷気の侵入に配慮されたモデルもあります。

さらに、ジッパーが寝袋の内側から操作できるようになっていたり、上下両側から開けられるようなダブルジッパー仕様になっていれば、より便利にもなり、暑い時期には足を出して寝られるため温度調節もしやすく、使い勝手はさらに向上します。

薄い生地をジッパーの上げ下げによって噛み込んで生地を傷めたりしないように、噛み込み防止機構が付いているモデルも。何の処理もされていない寝袋のジッパーはどうしても、ウソみたいに噛みやすいんです。

足元部分(フットボックス)の作り
寒さに敏感な足元部分(フットボックス)がゆったり立体的に縫製され、なおかつその部分に多めの中綿が封入されることによって、足元にかかる圧力が均一化し、保温性が向上。結果としてより快適な睡眠を可能にします。

寒さを感じやすい足元の羽毛を多めに封入。また足の形に合わせた立体的な構造が足全体を無駄なく均等に保温してくれる。
ポイント6:組み合わせて使用する寝具 ~快眠に必要なのは寝袋だけじゃない~
スリーピングバッグはそれ単体でも使えないことはないですが、濡れを防いだり快適さや保温性を最大限にするためにセットで使用する優れた道具が多く用意されています。中には必須のギアもありますので、それらは忘れずに準備しておきましょう。
スリーピングバッグカバー
ダウンの弱点は濡れたときの保温性の低下であることは前に述べたとおりですが、にもかかわらずアウトドアでは日常生活と違い、水濡れリスクが意外と多いもの。突然豪雨に見舞われた時にうっかりザックの中で防水していなかった、テント内で水をこぼした、結露した水が上から垂れ続けたなど、浸水の危険は忘れた頃にやってきます。気温が高い低山などでリスクが少ない場合を除き、雨の多い日本では何らかの防水対策が必須と考えるべきです。その第一は防水透湿素材のスリーピングバッグカバー(シュラフカバー)を別途準備すること。ちなみにこのカバーによって多少の保温性向上にもつながり、ちょっとした保温力増しにも役立ちます。

ライナー・シーツ
主に保温性の向上のためにスリーピングバッグの内側に入れるライナー(インナーシーツ)は、新たにシュラフを買うほどではないけど、手持ちの装備ではちょっと保温力が物足りないなと思うときなどに便利な場合があります。また昨今ではコロナ禍によって山小屋泊まりでもライナーシュラフが必須という山小屋も増えていて、衛生面・快適性向上といった目的でも利用が増えてきているのが実際です。
ともあれ何かと便利なライナーシーツは手軽でコンパクト、またそこまで高価でもなく使い勝手も良いため、1枚持っていて損はありません。素材はやはりコットンではなく化繊やシルクなどにしましょう。個人的にも長く重宝してたのですが、実はインナーとしてではなく夏用スリーピングバッグの代わりとして使っていたこともあります。学生時代から社会人数年目まではこれと3シーズン、スリーピングバッグカバーの組み合わせで1年間をやりくりすることも不可能ではありません。
ピロー
余裕があればアウトドアに便利な膨張式のピロー(枕)を使い、さらなる快眠に繋げるということも検討してよいでしょう。最近ではかなりコンパクトに圧縮できるピローもあるため、そこまで荷物に負担がかからなくなっているのは確かです。
ただ、空気で膨らませた枕は個人的にはそこまで快適とは思えず、苦労して持ってくるほどのものかどうかは人によるところが大きいのではないでしょうか。持っていかなかったとしても、着替えの衣類やタオルなどをスタッフバッグに入れるなどして即席枕を作ることもできますので、どうしてもというこだわりがなければ正直そこまで気にする必要はありません。

個人的にお気に入りのアウトドア枕はマットレスフォームの切れ端が詰まったTHERM-A-RESTのコンプレッシブルピロー。ただし山に持っていけるほどコンパクトにはならない。
スリーピングパッド
いくらフカフカのダウンでも体重には負けてしまい、地面に接する部分は硬くて寝心地が悪いばかりか多くの熱が逃げていき、寝袋の保温性能を大きく損なってしまうため、寝袋下にはマットを敷くのが必須です。スリーピングパッドも目的やスタイルによってさまざまなモデルがあり、自分に最適なモデルを選ぶためには多くのコツが必要です。
関連記事
まとめ
軽くて小さく、いつでもちょうどよい十分な暖かさがあり、なおかつ濡れや湿気にも強く丈夫で破れにくい。そんな夢のような寝袋があれば苦労はしないのですが、現実的には季節や用途に加え、暑がり・寒がりといった個々の体質や好み、組み合わせる他の装備などとの兼ね合いによって、それぞれにとってベストな寝袋というのは様々です。これはシュラフ(に限らず山道具全般)選びの難しさでもあります。ここで挙げたベストモデルは自信をもっておすすめできる優秀な寝袋ばかりですが、これをきっかけにぜひ自分ベストを探す楽しさも共有できれば幸いです。
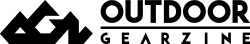
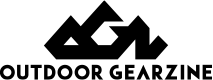


















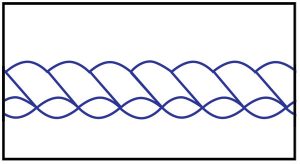
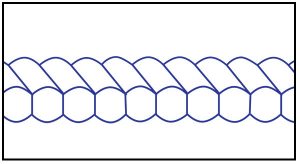
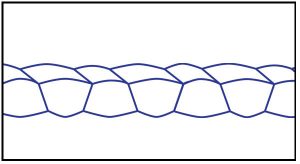
 どこまでも自由に山を楽しみたい人のための、ウルトラライトバックパックのベスト・モデルと、後悔しない選び方のポイント
どこまでも自由に山を楽しみたい人のための、ウルトラライトバックパックのベスト・モデルと、後悔しない選び方のポイント 【2025FW】簡単そうで意外とむずい。秋冬向けトレッキングパンツのベスト・モデルと、後悔しない選び方のポイント
【2025FW】簡単そうで意外とむずい。秋冬向けトレッキングパンツのベスト・モデルと、後悔しない選び方のポイント 「NEMOとみんなではじめるテント泊ハイキング」5月のテント泊イベントで体験できる予定の野営アイテムについて
「NEMOとみんなではじめるテント泊ハイキング」5月のテント泊イベントで体験できる予定の野営アイテムについて 【2025秋冬】ダウン?化繊?フリース?快適なレイヤリングのカギは素材選びから。登山向けミッドレイヤー(防寒着)のタイプ別ベスト・モデルと、失敗しない選び方のポイント
【2025秋冬】ダウン?化繊?フリース?快適なレイヤリングのカギは素材選びから。登山向けミッドレイヤー(防寒着)のタイプ別ベスト・モデルと、失敗しない選び方のポイント